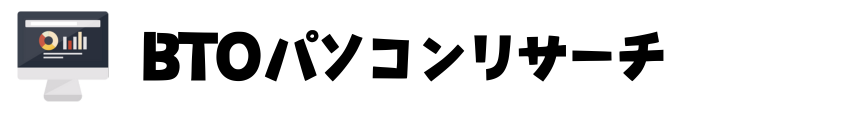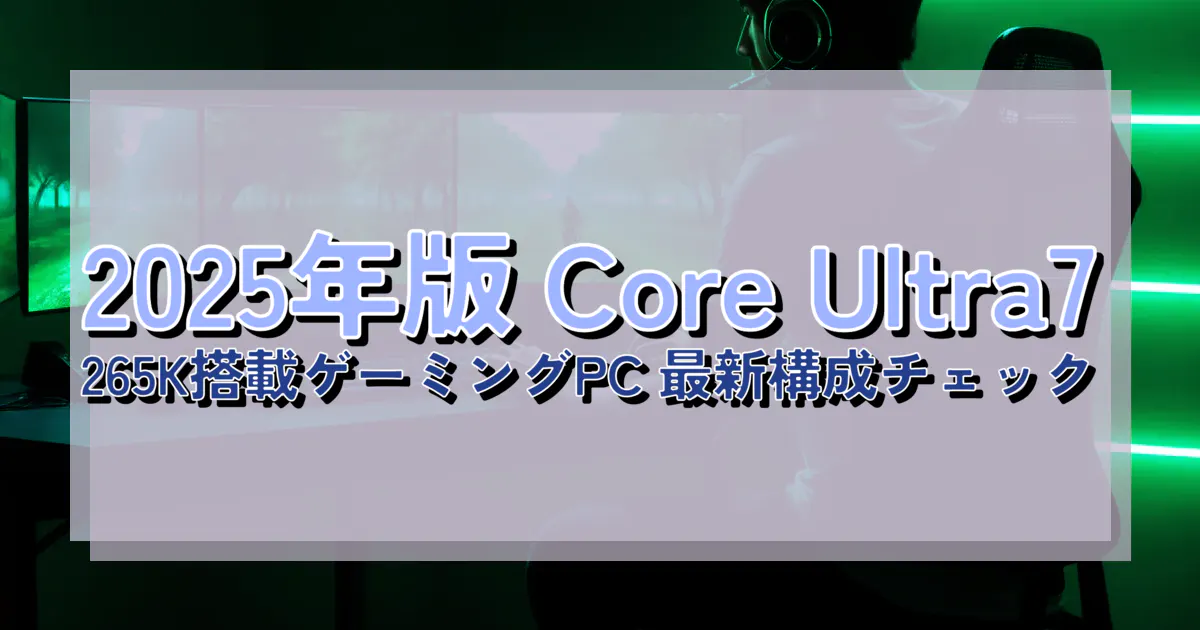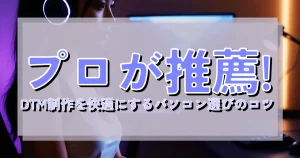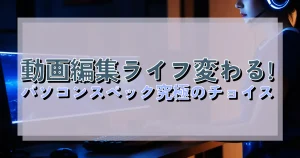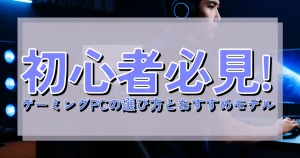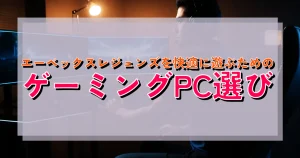Core Ultra7 265K ゲーミングPCの実力を実機でチェック

Lion Coveアーキテクチャを触って気づいたこと
私は普段から重い3Dゲームや顧客向けのデザインデータを扱うので、どうしてもCPUの限界を感じる場面がありました。
しかしこのCPUを使い始めてから、その「限界感」がふっと軽くなる瞬間に何度も出会いました。
正直なところ、この安心感はスペック表では見えない部分ですが、日々の作業を通じて「これは違う」と素直に思わされます。
ゲームの場面で言えば、重たいMMORPGを立ち上げて配信ツールを並行で走らせても、UIの応答がまったく途切れないのです。
前世代機ではどうしても「ここは妥協するしかないな」と思うような遅延が出ていましたが、このCPUではきっちり耐えてくれる。
その瞬間には「これはもう趣味用マシンじゃなく、間違いなく仕事道具にもなるな」と思わず声に出しました。
机に座りながら独り言を言ってしまう感じ。
また、Lion Coveのパフォーマンスコアは力強さがはっきりと伝わってきます。
長年「ゲームを動かすならCPUの力が要だ」と思ってきましたが、それを裏付けるように描画や物理演算の処理が崩れません。
負荷のかかるシーンで「お、まだ落ち込まないな」とちょっと笑ってしまう。
一見すると冷静に見える感想ですが、実際は心の中では拍手しているような気持ちです。
一方で、クライアントワークで使ってみた時も意外なほど快適でした。
私は「効率が上がれば残業が減る」と以前から思っていましたが、今回はそれを机上の理論ではなく、肌感覚で確認できました。
大げさな言葉ではなく、働き方に直結する違いです。
夜遅くまで残る必要が減れば、気持ちに余裕も生まれます。
冷却面でも改善が感じられました。
私は長らく水冷を当然のように使ってきましたが、このCPUでは空冷でも安心して動かせています。
DEEPCOOLの大型空冷クーラーを組み合わせたのですが、高負荷でも落ち着いた動作をしてくれました。
水冷を外したことでケース内の余裕も生まれ、掃除の手間も減った。
ただし注意も必要です。
ピーク性能を維持するには電源やエアフローに気を配らなければなりません。
ケース内の空気の巡りを考えずに組むと、本来の力を活かしきれない。
これは自作派の楽しさであり、同時に悩みのタネでもあります。
40代になり経験値も増えた分「ああ、ここが組む人の腕の見せ所だな」と苦笑する場面も増えました。
悪くない。
RTX5070やRadeon RX9070と組み合わせた時の相性の良さは際立っていました。
GPUの性能がいくら優れていてもCPUが足を引っ張ることがありますが、この構成ではそう感じません。
CPUがしっかりと基盤を支えてくれるので「この安心感は大きいな」と心底思いました。
単なる快適さを超えて、使いながら信頼関係を築いていくような感覚さえ覚えます。
AI処理用のNPUを試したときも驚きがありました。
動画解析や簡単な機械学習タスクを走らせても、GPUに比べて軽やかに処理が分散していくのを実感しました。
まだ発展途上の機能ですが、すでに実務で実験できること自体が大きなアドバンテージです。
私は仕事柄こうした新機能を試すのが好きで、「なるほど、ここまで実用に近付いたか」と嬉しくなりました。
最終的に私は、Core Ultra7 265Kを中心に据えた構成こそが当面の最適解だと考えています。
性能・安定性・省エネのバランスがよく、長期的な拡張性にも期待できるからです。
私にとってPCは道具であると同時に相棒なので、安心して任せられる存在は大切なのです。
静かに動いてくれる。
それでいて余裕もある。
この二つを備えていることは決して小さな価値ではありません。
仕事では余計な音が集中を削ぎますし、趣味のゲームでは静けさの中に没入感が広がります。
その両方を叶えてくれるCPUはそう多くありません。
だからこそ、私は胸を張ってこのCPUをすすめたいのです。
日常の積み重ねの中で「助けられている」と何度も思わされるからです。
性能比較の数値を超えたところで、確かに支えられている実感がある。
だから選ぶ価値があると私は断言します。
NPUによるAI処理はどんな場面で役立つのか
実際にCore Ultra7 265Kを使ってみて、その理由を深く実感したからです。
NPUという新しい処理ユニットが加わったことで、従来ではCPUやGPUに大きく偏っていた負荷が分散され、プレイ中の不自然なカクつきが大幅に減ったのです。
これは正直、単にベンチマークスコアの話ではなく、プレイヤー本人が体感できる大きな違いです。
ゲームに没頭していたときにふと「お、これ全然違うぞ」と感じた瞬間、私は心の中で小さなガッツポーズをしていました。
特に印象的だったのは配信を伴うゲームプレイでした。
以前は配信ソフトを立ち上げただけでCPU使用率が跳ね上がり、ゲーム内のフレームレートがガタ落ちすることが少なくありませんでした。
そのたびに視聴者に「ちょっと重いですね」と苦笑いしながら弁解する場面も多く、正直なところ悔しい気持ちもありました。
しかし今の環境では、NPUが音声処理やノイズ除去といった裏方の作業をきっちり担ってくれるので、CPUとGPUは描画や演算に集中できる。
結果的に映像は安定し、自分の入力も遅れなく反映される。
安心感ってこういうことかとしみじみ感じました。
もう一つ強く驚かされたのが、AIを活用することでNPCの動作そのものが変わってしまったことです。
昔からNPCの動きはある程度パターンが読めたので、相手の行動を先読みして攻略することができました。
ですが、最近の最新タイトルではAI学習を取り入れたNPCが、まるで人間のようにこちらの行動を予測して反応してきます。
その処理をCPUやGPUだけで担うと負荷が重すぎて動作が鈍るはずなのですが、NPUが効率的に分担してくれる。
そのおかげでゲーム全体が滑らかに進み、自宅でも本物のプレイヤーと対戦しているような緊張感に包まれる。
不思議ですが、数分もしないうちに私は「これはもう以前のゲーム体験とは別物だ」と思わされました。
具体的な体験を一つ挙げると、RTX 5070Tiとの組み合わせで3時間以上配信を行ったときのことです。
これまでは長時間の配信になるとPC内部の温度が上がり、ファンが常に全力で回り続ける。
それが耳障りで、集中力を削られることがしばしばありました。
しかしNPUが積極的に負荷を分担してくれるおかげで内部の温度上昇は緩やかになり、ファンの音が大きな問題にならなくなったのです。
しかもこれはゲームだけに留まりません。
普段の仕事でも恩恵を感じています。
私は仕事柄、資料を作りながら別画面で画像生成AIを走らせつつ、ブラウザで調べ物を同時並行で行うことが多いのですが、以前はPCがもたついてイライラする瞬間だらけでした。
それがNPUによってAI処理を肩代わりしてもらえるようになると、全体の動きが一気に軽やかになる。
小さいように見えて、毎日の積み重ねでは本当に大きな違いです。
毎日のストレスが減る。
もちろん課題も残っています。
すべてのアプリケーションがNPUに完全対応しているわけではなく、例えば旧来のソフトを利用すると従来どおりの重さを感じる瞬間もある。
しかし、対応しているソフトでの効率化を見ると「将来は確実に広がる」と信じられる。
実際、最新の動画編集ソフトで自動カラー補正をNPUに任せたとき、処理速度だけでなく色合いの自然さに思わず息をのむほどでした。
長年編集作業を趣味にしてきた私にとって、その瞬間はちょっと感動的で、未来の可能性を垣間見た気さえしたのです。
性能を重視する人も、安定性を重視する人も、どちらにとっても魅力のある構成。
ゲームの配信をしながら遊びたい人にとっても、日常的にクリエイティブな作業をしている人にとっても、大きな助けになる環境です。
私自身、この構成を試してみて「これを選ばない理由が見つからない」と素直に思いました。
PCというとスペック表の数字ばかりが注目されるのが常ですが、これからはNPUという新しい存在を軸に選び方が変わっていく。
裏方のように見えて、実際は次世代のPC体験を切り拓く主役になる存在です。
間違いなく、これからの基準になると私は確信しています。
未来の基準ですね。
高解像度ゲームでCPUがボトルネックにならないか試してみた
実際に手元で試してみた結果として率直に言えるのは、このCore Ultra7 265Kは4K環境で最新GPUと組み合わせた場合に、ほとんどCPUが足を引っ張らないという点です。
私も正直なところ、最初は「そんなに上手くいくわけがない」とやや疑っていました。
ところが実際に触ってプレイしてみると、その疑念があっけないほどに崩れ落ち、拍子抜けするくらい安心してゲームを楽しめました。
フルHDや2K程度の解像度でリフレッシュレートを非常に高く設定した場合、どうしてもCPU側が相対的に重くなり、GPUパフォーマンスが遊んでしまう場面がありました。
つまり極端な条件ではCPUの強みが揺らぐ瞬間もある。
ゲーマーとしては見逃したくない感触で、私自身「やはり万能というわけではないな」と妙に納得してしまったのです。
4K環境でのパフォーマンスこそ大きな見どころでした。
Cyberpunk 2077を最新環境で試した際、RTX 5090と組み合わせてもCPU使用率は40%台で留まり、GPU側が主導してリミットに達していました。
これは明確に「このCPUは舞台を壊さない」と伝えてくる瞬間です。
しかも同時にDiscordで通話や画面共有をしても一切問題なく、普通に話しながらゲームを楽しめる。
この余白や安定感には感謝に近い驚きがありました。
ビジネス面でも意味は大きく、例えば重いデータを処理しながら別作業を進めるような状況で、パソコンがびくともしないことで生まれる安心感。
それって仕事の集中力を保つ上で大きな価値になるのです。
ただし、理想的とも言えない部分ももちろんあります。
特に熱の問題です。
日常使いなら空冷でも十分に静かで冷えていますし、不安は感じません。
しかし以前に水冷環境を組んでいた経験からなのか、どうしても「もっとまだ冷やせるのでは?」と欲が出る。
そういう人間の性のような感情が顔を出すのです。
それでも冷却と静音性を同時に実現するバランスは非常に良く、設計の緻密さを実感させられました。
オーバークロックについても少し試してみました。
ただ、その分リスクを減らし、システム全体を安定させられると実感できたのは大きい。
結局は「やっぱり安定が一番」というところに落ち着くわけです。
これが40代になった自分の選択基準かもしれません。
Radeon RX 9070XTとの組み合わせでも驚かされました。
FSR4をオンにした環境でもCPUが足を引っ張ることなく、むしろ映像美の引き立て役に徹しています。
特に広がるオープンワールドの遠景描写は、まるで知らない風景を再び見つける感動に似ていました。
性能表では感じられない「情緒的な価値」が、画面越しにこちらへ迫ってくる。
技術の進歩が気持ちを揺さぶる瞬間というのは、やはり特別です。
では、どんな環境がこのCPUに最も合うのか。
やはり答えは4K、あるいは5Kと言えます。
8Kに挑戦してみましたが、GPUパワーが現状ついてこられず、CPUが持て余すような状態になりました。
CPUとGPUの能力が互いに自然に噛み合い、無理なく高品質な体験が実現するゾーンだと実感しました。
思わず口に出してしまったのは、「これなら配信も録画も余裕でいけるな」という一言です。
仕事の合間に重いExcelを処理しながら、ちょっと気晴らしに高負荷のゲームを立ち上げても、止まることなく滑らかに切り替わる。
それが当たり前のようにできる環境は、忙しい日常において本当にありがたい体験でした。
効率を求めつつも遊びも楽しみたい、そんな自分にぴったり合ったのです。
未来への期待もあります。
今後はAI支援がゲームに組み込まれていく流れが加速していくはずです。
その時にNPUを持つこのCPUは、間違いなく強力な武器となるでしょう。
ただ残念なのは、今のところソフトウェア側がこのAI機能を十分に活かせていないということ。
その壁を越えれば体験はさらに進化し、いま味わっている没入感を大きく超えると確信しています。
だから最終的にどう評価するかといえば、4K以上で真剣にゲームを楽しみたい人間にとって、このCore Ultra7 265Kを選ぶのは理にかなった選択だと私は思います。
CPUボトルネックの不安を忘れてしまえる環境が待っている。
未来を見据えた安心感と安定性、それがこのCPUの本当の強さです。
楽観ではない。
確信です。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 42777 | 2466 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42532 | 2270 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 41569 | 2261 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 40867 | 2359 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38351 | 2079 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38276 | 2050 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37049 | 2357 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37049 | 2357 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35430 | 2198 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35290 | 2236 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33552 | 2209 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32699 | 2239 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32334 | 2103 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32224 | 2194 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29074 | 2041 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28365 | 2157 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28365 | 2157 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25293 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25293 | 2176 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 22944 | 2213 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 22932 | 2093 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20726 | 1860 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19385 | 1938 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17621 | 1817 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 15947 | 1779 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15194 | 1983 | 公式 | 価格 |
Core Ultra7 265K 搭載PCと相性のいいGPUを探る

RTX5070TiとRX9070XTを使い比べて感じた違い
数字で並べられたベンチマークや製品比較では見えにくい部分が確かに存在していて、実際のプレイを通じて「ああ、これか」と腑に落ちる瞬間が何度もありました。
そして使い続けて分かったのは、結局のところ単純な性能比較ではなく、自分がゲームに求めるものがどこにあるかで選び方が大きく変わるということでした。
私がまず驚かされたのは、RTX5070Tiの反応速度です。
FPSを長くやってきた身として、入力への追従性は勝負を大きく左右します。
わずかにマウスを動かした瞬間、画面が即応してくれるあの感覚。
正直なところ「これなら一瞬の判断で勝敗が分かれる場面でも踏み込み切れる」と思いました。
神経をすり減らすような緊張状態で戦う時、この速さはほんの少しの安心をくれるんです。
たったそれだけで勝ち筋を拾えるケースがある。
FPSを本気でやってきた人には、この差がどれほど大きいか分かるはずです。
一方でRX9070XTはまるで方向性が違いました。
単純にフレーム数が高いことよりも、映像そのものの余裕があるんです。
オープンワールドを走っているときに、風景がふっと自分の視界に馴染む。
時間を忘れるんですよ。
レイトレーシングを効かせた街並みなどは美しいというよりも「そこに自分が居る」というリアルな感覚を与えてきます。
数字で説明できるものではなく、むしろ心に残る映像体験として訴えてくるタイプ。
これは大きな魅力でした。
AI処理の性格も異なります。
RTX5070Tiのニューラル系の技術は細部の陰影や微妙な光を描くのが得意で、例えば雨に濡れた夜道を歩くとき「ああ、こういう表現が欲しかった」と素直に実感できる。
対してRX9070XTはフレームを自然に補完して、途切れを感じさせずに映像を流してくれる力があります。
深夜に暗い森を探索しているとき、現実味のある映像の繋がりが妙に生々しくて、ふと背筋に寒気が走りました。
思わず「やられたな」と苦笑しましたよ。
消費電力の面も気づきが多かったです。
RTX5070Tiは比較的控えめで、長時間遊んでも安定感がある。
一方でRX9070XTはパワーをしっかり使うタイプなので、導入前は正直構えていました。
RX9070XTはもっと暴れるかと思っていたのですが、最近のケースや大口径ファンなら思ったより穏やかで、丁寧に扱えば十分現実的な選択肢です。
ゲーム体験として捉えるなら、RTX5070Tiは「どんな手を使っても一歩先に動きたい」というプレイヤーに最適です。
逆にRX9070XTは「楽しむ時間そのものを深く浸りたい」という人の選択肢になる。
単なる攻略スピードの問題ではなく、自分の気持ちの置きどころの違いなんです。
いや、むしろ正解が二つあると感じたんです。
CPUとの相性についても触れておくべきでしょう。
Core Ultra7 265Kと組み合わせた場合、どちらのGPUもボトルネックを感じさせませんでした。
むしろ「CPUがGPUをしっかり支えている」と思えたのは頼もしかったですね。
そのおかげで迷いなくGPUの特性を楽しめました。
体験を重ねる中で私はサッカーに例えるようになりました。
RTX5070Tiはフォワードのように素早く鋭く切り込み、試合の流れを一瞬で変える。
RX9070XTは中盤で落ち着いて全体をコントロールし、試合を形にしていく。
どちらもチームに必要な存在であり、役割が違うからこそそれぞれに意味がある。
だから選ぶ時に大事なのは、自分が試合でどんな役割を担いたいのか。
そこを意識するだけで答えははっきりするんです。
その両方が揃うこと自体がなんとも贅沢でした。
だからこそ最終的に強く言えるのは「どちらを選んでも後悔はない」ということです。
最終的に決め手になるのは、自分が勝ちにこだわるのか、それとも世界に浸りたいのか。
その一点です。
勝ちたいのか。
浸りたいのか。
私にとってはその選択の自由が、ゲームを楽しむことの本質だと思えました。
この違いを理解した上で、自分が一番納得できる方を選べることこそが喜びですし、それを味わえた私は幸せだと本当に思います。
コスパ重視ならRTX5060Tiでどこまで遊べるか
Core Ultra7 265Kを選んだ段階で、CPU性能について不満を抱く状況はまず考えにくいと私は思います。
むしろ問題になるのはグラフィックカードの選択肢です。
実際、多くの仲間が迷うのが「RTX5060Tiで本当に十分なのか」という問いでした。
私自身も購入前に同じことを考え、悩みました。
ただ、最終的に選んで良かったと強く感じているのは事実です。
RTX5060Tiの良さは、単に数字や公式スペックで説明できる部分以上に、コストと体験の質のバランスにあります。
最新のBlackwellアーキテクチャを採用し、GDDR7まで積んでいるのに、無理のない価格帯に収まっている。
正直、この時点で「よく作ったな」と感心してしまいました。
派手ではないけれど、きっちり働いてくれる存在感。
仕事仲間で言うなら、控えめだけど信頼できる同僚のようなものです。
Core Ultra7 265Kと組み合わせ、最新のAAAタイトルをWQHDで動かしました。
開始直後に感じたのは、安定という安心でした。
もう少し描画が厳しい場面があるだろうと構えていましたが、実際には問題が少なく、フレームレートも滑らかに保たれていたのです。
夜中にプレイしてもファンノイズが静かで、隣室の家族を気にせずに済んだことも大きな安心材料でした。
家庭でPCを使うなら、この静かさは相当に重要です。
5060TiはDLSS4を活用することでフレームを生成し、Reflex 2による低遅延も相まって、特にシューティングゲームでの応答がとても快適でした。
相手の一瞬の動きを見逃さず操作できるときのあの感覚。
これを体験すると、上位モデルでなければならない理由が自分には見当たりませんでした。
もちろん、4Kウルトラ設定で圧倒的な映像を追い求めたいなら話は別です。
その場合はもっと上を選ぶべきでしょう。
でも、私を含む多くのプレイヤーにとって必要十分。
それが5060Tiなんです。
加えて、消費電力や発熱がかなり抑えられている点も評価に値します。
空冷で充分に冷却でき、650Wクラスの電源で不安なく動作。
これは本当に大きい。
高性能GPUを入れるとケース内の熱対策や電源容量まで見直しが必要になり、予算も膨らみ、手間も増える。
正直、それを考えると気が重くなります。
ところが5060Tiはそういう煩わしさから解放してくれる。
ただ、弱点もあります。
4K設定のフルレイトレーシングは、このカードだけでは難しい。
ここは潔く認めるしかない部分です。
ただ最近の技術は賢く、DLSS4やシェーディング技術を組み合わせれば、実際の見た目では上位機との差を強く意識しないことも多い。
上位モデルの華やかな強さではなく、堅実に仕事をこなすバランス型。
私はこの性格に非常に親近感を覚えました。
特に印象的だったのは、新しいFPSをWQHDで試したときでした。
144Hzの滑らかな映像を目で追える瞬間。
「ああ、これはいい」と思わず声に出た瞬間。
本当にうれしかったです。
ゲームをただ遊ぶだけでなく、期待を超える体験をもらえるとき、人はこうして気持ちが動くものなんだと実感しました。
さらに、CPUとの組み合わせの余裕は大きな安心材料です。
将来的にもっと性能の高いGPUに切り替えるなら、その時もCPUを据え置ける強みがあります。
買い替えを検討するたびに、この安心感を思い出すでしょう。
それでも実店舗に行けば、売れ筋はRTX5070Tiです。
店頭デモを目にすると、確かにフレームレートの伸びを体感できます。
冷静に価格差と照らし合わせると「そこまで出す意味があるのか」と自分に問い直してしまいます。
昔のパーツ競争を思い出して懐かしい気持ちになりましたが、財布を握る立場としては、冷静な判断が求められます。
私の答えはシンプルでした。
5060Tiだな、と。
上だけを追えばキリがありません。
その欲望を満たしたいなら上位GPUが必要です。
しかし日常的に快適で無理のないPCライフを求めるなら、5060Tiが極めて実用的で、安心して長く付き合える存在になるのです。
改めて声を大にして言います。
このカードは贅沢すぎず、でも物足りなさもない。
それでいて手堅く結果を出してくれるのです。
だから信頼できる。
Core Ultra7 265Kと5060Tiのタッグ。
私は「これで間違いない」と心から感じています。
結局、安心して遊べる環境。
そして納得の価格性能比。
この二つを両立できるのが、5060Tiという選択肢だと私は断言します。
――それが私の結論です。
265K搭載PC搭載ゲーミングPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56AH

| 【ZEFT Z56AH スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster Silencio S600 |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54QJ

| 【ZEFT Z54QJ スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN SR-u7-6170K/S9

| 【SR-u7-6170K/S9 スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265K 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54W

| 【ZEFT Z54W スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265K 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5050 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN SR-u7-6160K/S9

| 【SR-u7-6160K/S9 スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265K 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
4Kゲーミングでも安心して使えるGPUを検証
4Kの解像度で本気で遊ぶなら、GPUの選択肢はとにかく最重要のテーマだと私は感じています。
むしろその余裕を支える役割を担うのがGPUであり、ここを中途半端にしてしまえば本末転倒になるのは明らかでした。
これが私の結論です。
では実際の選び方ですが、現状で私が安心して勧められるのはやはり最新世代の上位モデルに限られます。
GeForce RTX 5090や5080、あるいはRadeon RX 9070XT。
このクラスならグラフィックの設定を下げる必要がなく、余裕をもって4Kの世界を描ききれるのです。
価格面だけを見ればRTX 5070Tiも検討の余地はあるのですが、本気で遊びたいと考えるならやや力不足。
そこで私は妥協せずに上位モデルを選ぶ決心をしました。
実際に導入してみたのはRTX 5080でした。
FPSやオープンワールド系の重量級タイトルをプレイしたところ、レイトレーシングを最上限に設定してもカクつきを覚える場面はほとんどありませんでした。
操作感の滑らかさと映像の迫力には正直感動しました。
初めて試したときは「ここまで快適になるのか?」と心の底から驚きましたし、古い世代にはもう戻れないとその瞬間に悟りました。
DLSS 4の完成度も高く、映像の補完処理が自然すぎて人工的な違和感がゼロに近い。
一方でAMDのRX 9070XTも予想以上でした。
私はこれまでアップスケーリング技術の面でFSRがDLSSに及ばないと考えていたのですが、FSR 4を実際に試すとその認識は大きく変わりました。
特にスピーディーなカメラの切り替えや移動の多いアクションゲームでも補間の乱れが目立たず、プレイに集中しやすい。
初めて触れたときは「もうFSRを侮れない」と思わされ、AMDがここまで追いついてきた事実に心が動きました。
進化を実感した瞬間だったのです。
VRAMの容量についても触れておきたいです。
RTX 5090が搭載する24GBのメモリは圧倒的な安心感を与えてくれます。
これから数年、テクスチャのサイズがさらに膨らんでも余裕を残して戦えるだろうと考えられます。
他方でRX 9070XTは16GBと控えめですが、独自のメモリ圧縮やキャッシュ構造により期待以上に快適さを維持できていました。
容量だけを見れば劣っているのに、工夫の積み重ねがここまで結果を変えるのかと感心しました。
いい誤算です。
最終的にどのGPUが最適かと自分なりに考えると、シンプルな整理ができます。
予算無視で最高を目指すならRTX 5090、バランスの取れた現実解がRTX 5080、そしてAMDの存在感や独自路線を楽しみたいならRX 9070XT。
この三択です。
実際CPU性能がこれだけ安定している今、ボトルネックになるのはGPUしかありません。
だからこそ中途半端な選択は後悔のもと。
これは痛感しました。
私自身、最初の数週間はRTX 5080とRX 9070XTの間で本気で迷いました。
価格は近く、それぞれの強みがはっきりしているのです。
RTX 5080は安定感と完成度、それに加えてDLSSの自然さが魅力。
RX 9070XTはFSR 4の成長ぶりとAMDならではの割り切った最適化に心を惹かれました。
でも最終的に私はRTX 5080を選びました。
決め手は経験値とも言える安心感でした。
王道こそ正解だと腹を割って思えたんです。
鉄板の選択。
こうして試行錯誤を繰り返した結果、自信を持って言えるのは、Core Ultra7 265K環境での4Kゲーミングは少なくともRTX 5080以上のGPUが必須であるということです。
5090なら将来を見据えた余裕を持てますし、RX 9070XTもAMDという選択肢を改めて確実なものにしてくれます。
どれも高い次元でまとまっており、不満を抱かず楽しめる性能でした。
むしろ「進化ってここまで来たのか」と嬉しくなるほどです。
だからこそ私の答えは明快です。
妥協はしないこと。
これに尽きます。
ゲームという趣味を真剣に楽しむなら自分をごまかすわけにはいかない。
私はそれを身をもって学びました。
つまり、4Kで心からゲームの世界を堪能するための絶対条件は「妥協のないGPU選び」。
そう言い切れます。
もし同じように本気で遊びたいと考えるなら、遠回りせず覚悟を決めて選ぶことをおすすめします。
結果として、より長く安心して楽しめる未来が待っているのです。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48367 | 101934 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 31937 | 78073 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 29952 | 66760 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 29876 | 73425 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 26983 | 68929 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26330 | 60239 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 21804 | 56800 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19787 | 50483 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16451 | 39372 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 15888 | 38200 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15751 | 37977 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14542 | 34920 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13652 | 30859 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13115 | 32361 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10750 | 31742 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10580 | 28585 | 115W | 公式 | 価格 |
Core Ultra7 265K で快適に使うためのメモリとSSD構成
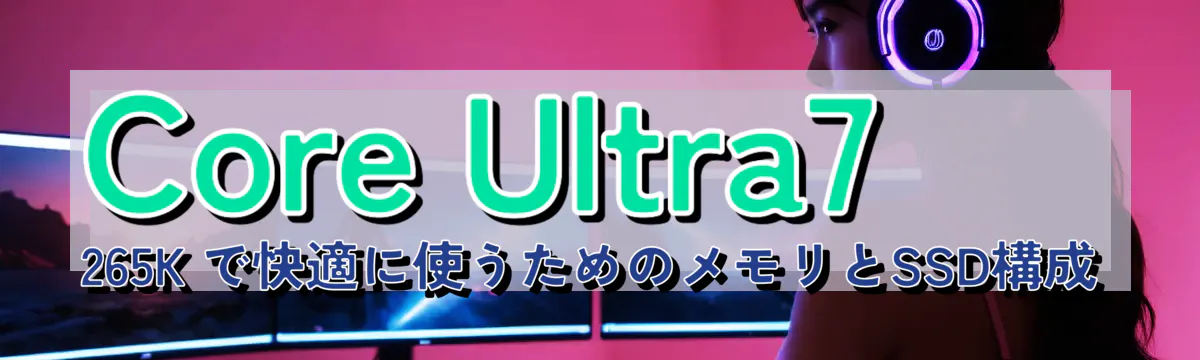
DDR5-5600は32GBか64GBか、どちらがベターか
ゲーミングPCにおいて、私は64GBを選択することが一番安心できる判断だと感じています。
最初は十分だと思い込めても、気づかぬうちに壁にぶつかる瞬間が必ずやってきました。
ゲームも作業も同時進行でこなすような私の生活には、32GBでは不安が残ったのです。
だから64GBに切り替えた時、初めて本当の快適さを知ったとさえ表現できます。
私は以前、Core Ultra7 265Kに32GBのDDR5-5600を組み合わせて使っていました。
当初は問題なく動き、PUBGやVALORANTのような比較的軽めのタイトルなら快適でした。
正直、その時は「これで十分に違いない」と自分に言い聞かせていました。
しかし重たいAAAタイトルや光の表現が美しいRPGを起動したとき、そして同時にChromeを開きっぱなしでDiscordを動かし、さらにOBSまで使い始めると、簡単にメモリ使用率が70%を超えてしまいました。
そこから先はフレームレートが落ちたり、動きがカクついたりする。
あの時の苛立ちは今でも鮮明に覚えています。
せっかくのゲーム時間が削がれる感覚。
これでは楽しいはずが楽しくなくなる。
そこで思い切って64GBに増設しました。
正直なところ、最初は「容量が倍になったところでそんなに変わるのか?」と半信半疑でした。
まず、バックグラウンドで複数のソフトを動かしながらゲームをしても全く不安を感じなくなったこと。
ブラウザを大量に開いたままでも、配信や録画を同時にこなしても全然問題がない。
切り替えてからは何度となく「ああ、これが余裕か」と思わず口にしてしまいました。
気持ちの余裕までついてくるんですよ。
広い帯域のおかげでCPUの負荷が高まる処理でも詰まり感が出にくい。
特にCore Ultra7 265Kのようにコア数が多いCPUをフルに使う作業では、その違いが本当に際立ちます。
私はゲームの合間に動画をエンコードしたり、AI系のツールを走らせたりもしますが、そういうときに64GBの余裕が頼もしい。
いや、本当に救われている感じです。
気になるコスト面についてですが、昔は64GBと聞くだけで敷居が高いと構えていました。
ところが今は違います。
私がBTOメーカーをチェックした際、32GBから64GBに増設するのに必要な差額は25,000円ほどでした。
以前だったらその値段に腰が引けていたでしょうが、性能の伸びや安心感を考えると「むしろ安く済む」と思えるくらいです。
財布へのダメージが大きすぎないなら、先に投資しておいたほうが後悔はない。
その直感は間違っていませんでした。
もちろん、すべての人に64GBが必要だとは言いません。
もし遊ぶのが軽めのeスポーツタイトルに限られ、他のアプリをほとんど同時に使わないなら32GBでも問題は少ないでしょう。
実際私もそうした時期はありました。
ただ、最近のゲームソフトは年々重くなっていますし、40代になった今では仕事の調べごとや連絡をゲームと同じパソコンで並行させることが多くなっています。
その環境下で「32GBで十分ですか?」と聞かれたら、胸を張ってうなずくことはできません。
メモリメーカー選びの話もしておきます。
CrucialやG.Skillの製品は定番ですが、私はSamsungの64GBを購入しました。
理由はひとつ、相性トラブルに悩まされたくなかったからです。
実際に導入してみると熱も安定し、システム全体がとても素直に動作しました。
ここまで安心して使えると、マシン全体が一体化したような感覚になります。
4K解像度で遊んでいても、もう心配はありません。
裏でブラウザを20タブ以上開き、仕事用の調べ物もしながらでも、何も気にせずゲームができます。
昔はゲーム用と仕事用のマシンを分けていましたが、今では一台で済ませられる。
そのおかげで時間効率が段違いに上がっています。
この変化は大きい。
32GBはとりあえず動かすには十分ですが、64GBにして初めて「余裕をもって快適に使える」環境が完成する。
Core Ultra7 265Kを軸に構築するなら、迷わず64GBで間違いありません。
数字上の違いに見えて、実際は体験価値に直結する差です。
自分の時間を大切にしたい人には、強く64GBをすすめたい。
安心感が違うんです。
安定感が違うんです。
この二つが、長時間パソコンと正面から付き合う私たちにとっての最大の価値だと信じています。
Gen5 SSDとGen4 SSDの体感速度差を比べてみた
なぜかというと、私自身が実際に両方を試してみて、その差を「期待外れだった」と心から思ったからです。
特にゲームのロード時間に関しては、性能表で示される数値ほどの体感差はなく、数秒わずかに短くなる程度。
これを価格差や発熱のリスクと照らし合わせると、どうしても「今選ぶべきはGen4」と結論づけざるを得ません。
たしかにGen5 SSDが持つ理論性能は見た目にも豪華で魅力がありますし、数値上は間違いなく速い。
しかし実際に巨大なプロジェクトデータをコピーしたときや、動画編集でキャッシュ処理を走らせたときにようやく「ああ、そうきたか」と思える程度で、ゲーミング用途では拍子抜けしました。
期待感とのギャップに正直がっかりしたんです。
なぜそこまで体感に差が出にくいのか。
ロード時間に関しては複数の要素が絡み合っていて、SSD速度だけでは劇的に短縮できない。
つまり「SSDだけが突出して速ければ快適になる」という単純な話ではないのです。
ここは多くの人が誤解しがちですが、実際に触ってみれば納得できる部分です。
ただし未来に目を向ければ話は別です。
マイクロソフトのDirectStorageの仕組みが広まれば、Gen5 SSDの真の力が発揮される可能性があります。
CPUを介さずGPUに直接データを渡せるようになれば、今までボトルネックだった部分が解消される。
そうなった時、今は蓄えているだけに見える性能が一気に活かされるでしょう。
その時こそ「待ってました」と笑顔になる瞬間が増えるはずです。
そんな位置づけにGen5はあるように感じます。
ただ現実を見ればGen5 SSDには大きな課題がある。
それが発熱です。
私も実際触ってみて「これは危ないな」と手に汗をかきました。
アルミのヒートシンクをつけても冷えず、急いでファン付きの専用ヒートシンクを取り付けてようやく落ち着いた。
PCケースの横に手をかざすとぬるいどころではなく、熱気がふっと顔をかすめてきた。
あれは恐怖でした。
高性能であるがゆえに熱との戦いが伴う。
それを実感しました。
性能はすでに十分で、読み込み性能も7,000MB/s前後あれば日常のゲーム用途には不足なし。
動画編集やちょっとしたプロジェクトでも、体感で困る場面はそうそうありません。
しかも価格も下がってきており、2TBでも手頃に買える。
扱いやすさと負担の少なさ、そのバランスが大きな武器です。
これなら「安心して任せられる」と胸を張って言えるんです。
もちろん人によっては「最新の規格を持っていること自体が満足」という気持ちもあるでしょう。
私もその感情は理解できます。
自作PCの世界では理屈抜きで新しいものに追いつきたくなる瞬間がある。
自分でも理性で「必要性は薄い」とわかっているのに、気づけばポチってしまいそうになる。
そういう誘惑は誰にでもあるものです。
それでも冷静にコストとのバランスを考えると、まずはGen4 SSDで十分。
たとえばCore Ultra7 265Kを組み合わせたPCにGen4の2TBを積めば、ゲームも動画作業も困らない。
そこに特別な作業や個人のこだわりがあるなら、追加でGen5を副次的に導入すればいい。
あくまで「必要なところに投資する」。
それが大事です。
運用の安定性を保ちつつストレスも少ないですからね。
ゲームが中心ならGen4。
特殊な機能を生かした作業をしたいならGen5を後から。
これが実際に試しながら私がたどり着いた答えです。
突然Gen5だけに全投入しようものなら、出費は増えるし、熱対策の負担も大きい。
それに対して得られる効果は数秒程度。
割に合わないな、というのが正直な気持ちです。
とはいえ将来を意識してGen5を入れておくことが無駄だと言うつもりはありません。
ですが私からの提案はシンプルです。
まずはGen4 SSDをしっかり選んで快適な土台を築くこと。
それで日常的な安心を確保できる。
そのあと余裕が出た時にGen5を追加する。
そういう段階的な導入こそが現実的で、長く安定してPCを使える方法だと感じています。
安心感って大事なんです。
安定性がすべて。
最終的に私が言いたいのはこれです。
今、最も現実的で誰もが納得できるのはGen4 SSDを中心にすること。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
ストレージは1TBで足りるか、それとも2TBが安心か
ストレージ容量で悩む人は意外と多いのではないでしょうか。
パソコンを新調するたびに「今回は十分だろう」と思って容量を選ぶのですが、結局後から「足りない」と感じてしまうことが何度もありました。
結論から言えば、2TBを最初に選んでおくことが、長く使う上で一番安心で効率的だと実感しています。
1TBでも最初の数か月は快適でした。
ゲーム数本と日常的なデータの保存であれば特に不満もなく、「十分だな」と思ったものです。
気がつくと容量不足に陥って、泣く泣く古いゲームを削除する羽目になる。
それが何より面倒で、正直ストレスなんですよね…。
数年前、私はBTOで1TBのSSDを選んだことがありました。
半年くらいは問題なくて「やっぱり1TBあれば十分だ」と安心していたんです。
ただ新作をいくつか追加して、さらに動画キャプチャを保存したら一気に状況が悪化しました。
10分程度の録画で数GB消費しますから、数十本も残せばすぐに埋まる。
そのとき外付けSSDを急いで買うことになったのですが、「どうして最初に2TBにしなかったんだ」と自分を責めたものです。
後悔。
それ以降は最初から容量を多めに積むようにしています。
特にゲーム用途では余裕があることが何より大事だと痛感しました。
SSDは容量が一杯に近づくとパフォーマンスが落ちやすく、実際に体感するほど全体の動作がもたつくこともありました。
たとえ空き容量が100GB残っていたとしても、実使用感は「ほとんど限界」という息苦しさなんです。
だからこそ、心の余裕のためにも大きめを選ぶほうがいい。
速度の話もよく耳にします。
PCIe Gen.5は確かに速いですが、値段も高く、発熱も気になる。
私は実際にゲーム中に速度差を大きく感じたことはありません。
それよりも快適さを決めるのは容量の方だと考えています。
「高速で容量不足」より「速度は十分で余裕の2TB」の方が、はるかに心地よい。
それが私の正直な答えです。
私の周りでもCrucialやWDのSSDを選んでいる人が多いです。
私自身もCrucialの2TB SSDに切り替えてから、容量不足に悩まされることが全くなくなり、精神的にもかなり楽になりました。
速度は十分で安定しているし、容量を気にしなくていいという安心感は大きい。
これは本当に「買ってよかった」と実感できた瞬間でした。
自由さ。
考えてみれば、今後ゲームのサイズが軽くなる未来は想像できませんよね。
グラフィックはどんどん進化し、解像度も上がり、テクスチャのデータは肥大化し続ける。
むしろ容量不足で設定を下げて遊ぶのは本末転倒だと思います。
せっかく高性能なPCを買うのに、それでは逆にストレスだと感じます。
容量が不足すれば遊びたいゲームを削除してはインストールし直す…という不毛な作業が発生します。
これ、やってみると本当に時間の無駄ですし、気持ちまで萎えてきます。
PCは楽しむために買うものなのに、容量管理のために頭を悩ませるようになったら間違いなく本末転倒です。
だから私は「余裕がある容量は快適さそのもの」だと声を大にして言いたい。
「じゃあ2TBをいつ導入すべきか」と問われれば、私は迷わず「最初から」と答えます。
後から増設すればいい、と言う人もいますが、外付けや追加のSSDはコストも労力も余分にかかりますし、配線や管理の手間も増える。
最初から2TBを選んでおけば、こうした不安や余計な作業を避けられて、長期的に見ても結果として経済的です。
経験から確信しています。
SSDはGen.4で構いません。
重要なのは容量と安定性、そして信頼できるメーカーを選ぶこと。
快適に遊びたい、効率的に仕事をしたい、容量でいちいち悩みたくない。
そんな願いを叶える選択肢として、2TBは「余裕ある安定の解答」だと私は思います。
これに尽きます。
長時間安定稼働のカギとなる冷却とケース選び
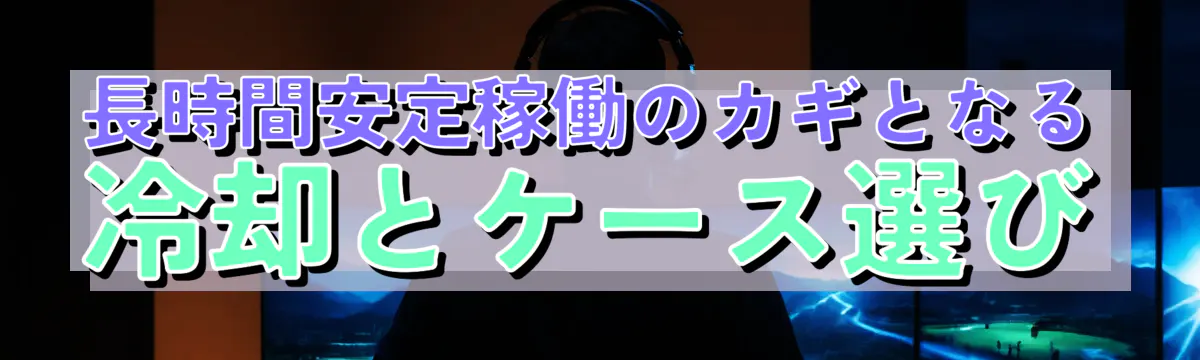
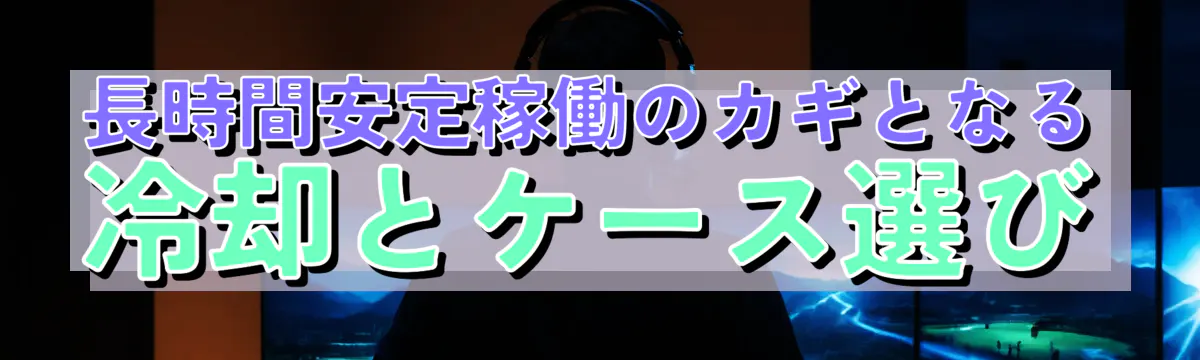
空冷と水冷を実際に使って感じた扱いやすさの違い
特にビジネス用途では一瞬のトラブルが大きなロスにつながるため、「とにかく安定して動く」ことが何より大事になります。
空冷の魅力はその一点に尽きる。
例えばCore Ultra7 265Kのような比較的新しいCPUを大型の空冷ファンで冷却すれば、多少のオーバークロックなら難なくこなせる安心感があります。
その安心感、これが本音です。
掃除に関しても空冷は手間がほとんどありません。
数か月に一度ファンのホコリをさっと取り除けば、延々と安定して稼働してくれるのです。
正直な話、出張や打ち合わせに追われる毎日の中で、手間のかかるメンテナンスに時間を割く余裕は多くありません。
だからこそ省エネルギーにも感じられるシンプルな空冷に、私は大きな魅力を感じます。
一方で、水冷にはやはり特別な存在感があります。
見た目からして力強さを主張し、「さあ、ここから本気でやるぞ」というムードが滲み出ます。
静かなんです。
夜のオフィスで一人キーボードを叩きながら、「静かで助かるな」とつぶやいた自分を今でも覚えています。
しかし水冷には、常に心配がつきまといます。
ポンプの寿命、冷却液の減少。
そのリスクは実際に経験して、重みを知りました。
以前、出張帰りにPCから妙な異音がして、スーツ姿のまま慌ててケースを開けたことがありました。
ポンプの異常音でしたが、そのときの不安感といったら本当に冷や汗ものです。
まるで大事な会議直前にスマホが急にフリーズするかのような焦燥感でした。
取り付けに関しても違いは顕著です。
空冷の場合は、重量のあるクーラーでも取り付けに必要なのはネジをきっちり締めるだけで済みます。
ところが水冷の場合、ラジエーターの位置決めやホースの取り回しをミスると台無しになり、予想以上に時間を奪われます。
特にガラスパネルのケースを選んでしまうと、見栄えを壊さないよう配線を処理するのに神経をすり減らすのです。
ようやく完成したときは達成感に包まれるけれど、「二度と短時間ではやりたくないな」とため息が漏れるのも事実です。
壊れたときのリスクもまた忘れられません。
しかし水冷ではポンプが停止した瞬間、熱が一気にこもってしまう。
最悪の場合システムがダウンする。
まさに、優勢に試合を進めていたボクサーが、不意の一撃でマットに沈むような展開。
あの一瞬の怖さを想像するだけで、背筋が冷たくなるのです。
それでも水冷の意義がないわけではありません。
RTX5090のような超ハイエンドGPUと併用する場合、CPUとGPUの両方を効率的に冷やす仕組みとしては確かに効果的です。
さらに大型ケースと組み合わせれば、冷却性能と見た目の両方で圧倒的に映える。
夢があるんです。
私は最終的にこう整理しています。
日常的に安心して任せられるのは空冷。
限界性能を狙い、趣味として楽しむなら水冷。
そう割り切れば悩みはなくなるのです。
大切なのは自分がPCに何を求めるか。
つまり状況次第なんですよ。
私はこの二つを実際に使い分けながら、そのときの自分に合った選択を続けています。
安心感が必要なときには空冷。
挑戦したいときには水冷。
265K搭載PC搭載ゲーミングPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN EFFA G09H


| 【EFFA G09H スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 128GB DDR5 (32GB x4枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II White |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54QJ


| 【ZEFT Z54QJ スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55BY


| 【ZEFT Z55BY スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | LianLi O11D EVO RGB Black 特別仕様 |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel Z890 チップセット ASRock製 Z890 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 1300W 80Plus PLATINUM認証 電源ユニット (ASRock製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55HV


| 【ZEFT Z55HV スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | intel Z890 チップセット ASRock製 Z890 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 1300W 80Plus PLATINUM認証 電源ユニット (ASRock製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54ATC


| 【ZEFT Z54ATC スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7800XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake Versa H26 |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
ピラーレスケースを試してみて分かったメリットと注意点
実際に使ってみて私が一番強く感じたのは、メリットとデメリットがはっきりと同居しているという現実でした。
華やかな見た目に惹かれて選んだものの、思い通りにいかない部分は確かにあります。
ただそれでも「これは使ってよかった」と心から思える瞬間があったのも事実です。
最初に胸を打たれたのは、ケース越しに覗く視認性の高さでした。
これまでのケースではフロントやサイドにある支柱が邪魔をして、せっかく組んだパーツもどこか窮屈そうに見えて、完成したPCが誇り切れないような感覚があったのです。
しかしピラーレスケースに変えてからは、そうした視界のノイズが一切なくなり、自分が構築したパーツ群を真正面から堂々と眺められる。
その感覚は、まるで長年の肩こりから一気に解放されたかのようでした。
家族に「ショーケースみたいだね」と言われた時には、胸が少し熱くなったのを覚えています。
特にGeForce RTX 5070Tiのように物理的な存在感を放つGPUを収めた際の高揚感は格別で、一瞬でPC全体がランクアップしたように感じたのです。
あの時の誇らしい気持ちは、今も忘れられません。
もう一つ強調したい良さは組み立てやすさです。
例えば内部の支柱に手をぶつける、長いグラフィックカードがうまく差さらず変な角度から押し込む、そんな場面ばかりです。
けれど今回のケースではそうした小さなストレスから解き放たれ、冷却パーツの配置にも余裕を持てました。
ラジエーター、ファン、さらにはケーブルの取り回しまでが格段に楽になる。
その上で空気の流れを自分なりに考えて整理することで、思った以上に温度管理が安定して、長時間使っても安心できるようになったのは実に大きい収穫です。
ただし課題もあるのです。
まず感じたのは重量でした。
ガラスパネルをふんだんに使っているため見た目は洗練されているのに、ひとたび持ち上げようとすると驚くほどの重さが身体にのしかかります。
若い頃なら気合いで持てたでしょうが、40代ともなると腰や腕に響くんですよね。
正直「引っ越すのが憂鬱だ」とため息をついたほどです。
さらに冷却面でも不安があります。
デザインが美しい分、密閉感が強いため、気を抜いて配置すると夏場は簡単に熱が籠ってしまうのです。
部屋の換気が弱いとゲームを始めて10分もすれば温度上昇が手に取るように分かる。
これは環境によっては致命的なリスクになり得ると痛感しました。
加えて、入手のしづらさという問題もありました。
国内ではすぐにポンと買えるケースではなく、限られたショップに頼らざるを得ません。
私が手に入れたLian Liの製品は品質そのものには満足しましたが、価格が高めで「もう少し手頃ならもっと広まるだろうにな」と思わず口に出しました。
こうした部分は、純粋にユーザーとして歯がゆいところです。
それでもこのケースにしかない輝きは確かに感じます。
ガラス面を通して映えるRGBライティングは、ただ光っているだけではなく「このPCは私のものだ」という強烈な実感につながりました。
その光を眺めている自分をふと客観視したとき、仕事での疲れや日常の慌ただしさから少し抜け出して、自分の趣味や時間がここにあるのだと嬉しくなったのです。
これは単なる光景ではなく、精神的な充足感でもありました。
私はそこで気づきました。
これは所有欲を満たす道具でありながら、同時に「作品」を展示する舞台なのだと。
ただ美しいだけでは終わらず、自分が時間をかけて丁寧に組み上げた構成が一つの表現になり、それを眺めたときにしか得られない特別な幸福感がある。
「これぞ自作の楽しさだ」と、我慢できず声にしていました。
もちろん、そんな満足感を味わうためには努力がいります。
冷却の工夫は欠かせませんし、設置する部屋や机の強度まで考慮しなければいけません。
気軽に「見た目がかっこいいから」という理由で選ぶと、後で大きな代償を払うことにもなりかねない。
その覚悟さえあれば、他に代えがたい唯一無二の体験が得られるのも事実なのです。
最終的に整理すると、このピラーレスケースは最新のゲーミングPCを組む上で、非常に魅力的なオプションであることは間違いありません。
外観の美しさに多少酔いしれても良いですが、それだけでなく冷却や使い勝手をしっかり調整すれば、確実に生活を支える頼もしい存在になります。
見せて誇れる喜びと快適に使える実用性を同時に抱えたケースはそう多くありません。
だから私は不便を承知でこのケースを選び、その選択に後悔はなかったのです。
やっぱりこれは自作の醍醐味なんですよ。
そして何より、電源を入れて光が走る瞬間に湧き上がる高揚感。
電源容量やエアフロー設計が性能に響くワケ
高性能なパソコンを組み立てるとき、ついCPUやGPUの数字にばかり目を奪われがちですが、私が本当に大事だと感じているのは電源とエアフローです。
これは単なる理屈ではなく、実際に失敗を経験して痛感したことです。
いくら高価なグラフィックボードや最新世代のCPUを用意しても、電源が不安定だったりケース内の通気が悪ければ、宝の持ち腐れになってしまう。
その事実を思い知らされたからです。
結末だけを言えば、土台を甘く見れば一瞬で投資が無駄になります。
私の過去の失敗の例をお話ししましょう。
数年前、定格出力だけを見て安価な電源ユニットを購入したときのことです。
当初は特に問題を感じませんでしたが、夏場の長時間ゲームプレイ中に突然のシャットダウン。
画面が真っ暗になり、膝の上で操作していた手が一瞬止まったあの衝撃は忘れられません。
まさに「節約する場所を間違えたな…」と頭を抱えてしまいました。
電源に関して言えば、ただワット数が大きいだけでは役に立ちません。
必要なときに必要な電力を安定供給できる信頼性こそが重要なのです。
特に最新世代のGPUは電力の変動が激しく、瞬間的に大きな電力を求めるため、ここを軽視すると不具合の温床になってしまいます。
ですから、認証を受けた高品質な電源を選び、容量にも余裕を持たせることが結果的には安心への投資になります。
数字に踊らされず、実用性を一番に考える。
これが今の私の確信です。
そして、もう一つの大きな落とし穴がケース内部のエアフローです。
これを軽んじると確実に痛いしっぺ返しを食らいます。
私は以前、見た目に惹かれてガラス張りの小型ケースを選び、高性能パーツを詰め込んだことがあります。
当初はその美観に満足していたのですが、真夏にプレイしてみると数時間でパソコンが何度もフリーズしました。
正直「冷却不足がここまで露骨に効くのか」と愕然としました。
あのときの失望感はいまだに記憶に焼き付いています。
エアフロー設計は単なるファンの有無ではありません。
吸気と排気のバランス次第で、まったく異なる結果になるのです。
見た目重視でガラスを多用したケースは格好良く、リビングに置いても映えます。
しかしその分、空気の通り道が作りづらくなるのは否めません。
その反省から私は結局シンプルなケースに戻しました。
その結果がどうだったか。
数時間ゲームを続けても温度は安定し、ファンの音も抑えられました。
「やはり道具は外見より実用性だ」と心から思いました。
安定感は快適さの根源です。
さらに最近はストレージの発熱問題も無視できなくなっています。
NVMe Gen.5のSSDを使うと、想像以上に熱を帯びるのです。
私は当初ヒートシンクを軽視していましたが、結果としてサーマルスロットリングに悩まされ、パフォーマンスを満足に発揮できませんでした。
そこでようやく、このパーツは「対策前提で使うべきもの」なのだと理解しました。
準備を怠らなければ、本来の性能を安心して引き出せるとわかった瞬間でした。
私は昔から「格好より実用」派ではありますが、ケースや冷却の失敗を通じてその価値を再確認しました。
もちろん、デザインに惹かれる気持ちも否定はできません。
使うたびに高揚感を与えてくれるのも事実です。
ただし、いざ実際に長時間ゲームを動かしたとき、うるさいファンの音や高温でフリーズとなれば、残るのは後悔と疲れだけです。
どんなに見栄えのするケースも、快適さを損なってしまえば意味がない。
だから私はあえて実務的な設計を優先する選択を取ります。
結果として、私が行き着いた結論は明快です。
CPUやGPUと同じレベルで電源とエアフローを真剣に考えること。
いくら強力なパーツを積んでも、土台の整備が甘ければ本来の半分すら力を発揮できません。
それは高層ビルを豪華にデザインしても、基礎工事が杜撰ならすぐに亀裂が入ってしまうのと同じです。
土台をしっかり築いた上でこそ、未来へ安心して投資できると私は確信しています。
だから私は今、パーツ選びで必ず二つの条件を守っています。
電源はピーク消費電力に少なくとも100Wの余裕をつけて確保すること。
そしてケースは見た目より冷却性能を優先することです。
シンプルに思えるかもしれませんが、この二つがあるだけで劇的に安心感が変わります。
どうしても外観を重視したいのであれば、その分冷却に工夫を加えたり追加投資を惜しまない覚悟が必要です。
そうでなければ、本当に欲しかった「快適で安心のゲーム体験」からどんどん遠ざかってしまいます。
性能を引き出しつつ心地よく長く使えるパソコンを作るには、電源とエアフローこそが影の主役です。
見映えに寄り道したくなる気持ちを抑えつつ、根幹を固めること。
それが結局のところ一番の近道なんだと、今の私は胸を張って言えます。
Core Ultra7 265K ゲーミングPC購入前の気になる疑問
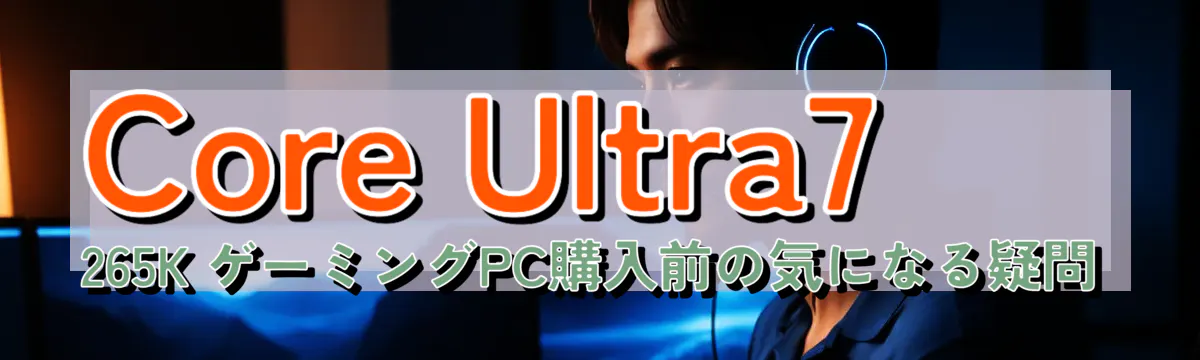
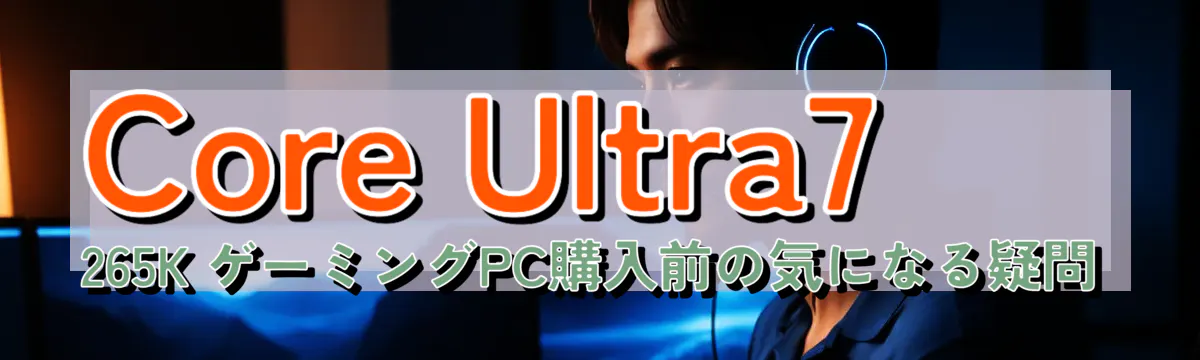
RTX5060Tiで最新ゲームを快適に遊べるか
RTX5060Tiは、私にとって現実的かつ納得のいく選択肢です。
正直なところ、若い頃のように性能を追いかけて財布を痛めつける時代はもう終わりました。
そういう付き合い方の方が自分には合っていると感じます。
フルHDやWQHDでのプレイにおいては、描画設定を変更する必要をほとんど感じません。
これは以前の世代のGPUと比べれば天と地の差です。
昔は「あと少し滑らかさが欲しいな」と思いながら設定をいじっていましたが、RTX5060Tiに変えてからは、その調整に費やす時間がほとんどなくなりました。
シンプルに、快適。
遊ぶことに集中できるようになったのは大きな価値だと思います。
ただし、4Kになると話は変わります。
重たいタイトルでは力不足を感じることもあり、「まだ厳しいか」とため息をつくこともあります。
ただ、DLSSを組み合わせれば驚くほどプレイアブルになります。
技術の進化ってすごいなと素直に思いました。
楽しめるレベルまで引き上げてくれる。
挑戦できる余地があることがうれしいんです。
特に印象的だったのは雨の日のレースゲーム。
フロントガラスを伝う雨粒や街路樹の影が夜の道路に映り込む瞬間、そのリアルさは思わず「いや、これは本物か?」と声が出るほどでした。
長年旧世代のカードで、それこそ荒い映像に我慢しながら遊んできた私には衝撃でしかありませんでした。
あの体験でこのカードが自分に合うと確信しました。
痺れました。
もちろん、RTX5070Tiと比べれば性能面で劣ります。
4K最高設定で最新FPSを遊ぶには力不足です。
これは疑いようのない事実です。
しかし私は妥協ではなく、選択だと捉えています。
自分にとって必要な性能と不要な性能を見極めて投資する。
それが今の私のスタイルです。
何もかも全力で追いかける余裕はない。
人生経験で学んだ知恵のひとつです。
割り切り。
これが大事です。
この価格でこの性能を出せるなら、悩む余地は少ないのではないでしょうか。
特に学生や社会人で限られた予算しかない人にとっては、非常に納得感のある選択肢だと強く感じます。
私自身も「これで良い」と心から思える一枚です。
信頼していい水準。
正直、AI処理なんて自分には関係ないと思っていたのですが、実際には配信時の画質改善やノイズ除去に威力を発揮してくれます。
オンライン会議で雑音が減り、相手の声を聞き取りやすくなったおかげで仕事のストレスが減りました。
生活そのものが楽になるとは想定外でした。
冷却性能についても満足しています。
ファンの音が気にならないのは、本当に助かるんです。
暑い季節になると以前はファン音が耳障りで気持ちが乱れることもありましたが、このカードは驚くほど静か。
落ち着いた気持ちでプレイに集中できます。
静寂のありがたさ。
私は逆に「5070に届かない」という点をメリットだと考えています。
なぜなら多くの人が求める標準的な環境はフルHDやWQHDであって、4K環境を必要とする人はまだ少数派だからです。
つまり、必要以上にお金をかけない分だけ、満足度の高い環境を無理せず整えられる。
現実的な選択の方が幸せになれると、私は感じています。
理想的な組み合わせはCore Ultra7 265Kです。
CPUとの釣り合いが良く、配信しながらでも快適にゲームができる環境になります。
あまりに快適なので気付けば夜更かししている自分がいて、それがまた嬉しい悩みになっています。
最上位GPUを手に入れることがゴールではないと今の私は思います。
むしろ価格と性能のバランス、それからAIやDLSSといった最新技術のサポートをしっかり備えて、現実的に多くの人が楽しむ視点に寄り添っているのがRTX5060Tiです。
その意味で、このカードこそ一番実用的で、安心して選べる存在だと自信を持って言えます。
余計な迷いは必要ありません。
RTX5060Tiで十分です。
メモリは32GBで十分か、それとも64GBで余裕を持たせるべきか
ゲーミングPCのメモリを32GBで済ませるか64GBにしておくか、この判断は多くの人がつまずくポイントだと思います。
少なくとも私はそうでした。
最初は「どうせゲームしかしないんだから32GBで十分だろう」と軽く考えていましたが、実際に使い続ける中で、その考えは少しずつ揺らいでいきました。
最終的に64GBを選んだのは、単なる余裕の確保ではなく、自分の日常に安心を取り戻すための決断だったのです。
最新タイトルを4K画質の最高設定で試してみました。
32GB環境でも何の問題もなく動き、フレームレートも安定していたので、その瞬間は「やっぱりこの構成で大丈夫だな」と胸をなで下ろしたんです。
ところが同時にブラウザで調べものをしながら、配信ソフトを立ち上げて、さらにDiscordで友人と話していると、メモリ使用率が一気に70%を超えてしまいました。
その数字を見た時、背筋が冷たくなるような感覚を覚えたのを今でもはっきり覚えています。
そう気がついた瞬間でした。
仕事でも同じです。
ギリギリのリソースでやっていると、必ず予期せぬ障害が発生して焦りに飲まれます。
例えば大事な会議の直前にPCが急に重くなり、資料を思うように操作できなくなったことがありました。
あのときの焦燥感と苛立ちは、言葉にならないくらい嫌な記憶として残っています。
普段は快適でも、裏でいくつものタスクを抱えると、とたんに足をすくわれる。
展示イベントで64GB搭載のPCを試す機会がありました。
来場者の多くは最初こそ「32GBと特に違いは感じない」と言っていましたが、実際に配信や録画を同時進行しはじめると「これ、32GBじゃ追いつかないかもしれない」と声を漏らしていました。
具体的に言えば、最新のGPUが生み出すフレーム生成を使いながら4K配信を行うときです。
32GBではわずかな遅延が発生する一方で、64GBではまるで何もなかったかのように滑らかに動き続ける。
その差は一瞬の体感でしかないのに、実際に触れてしまうと、もう元には戻れません。
小さい差が大きな安心に変わるのだと痛感しました。
もちろんコストは悩みどころです。
正直に言って、そのお金をGPUやストレージに回した方が快適度は高いと思っていました。
私も当初は「メモリにそこまで投資するのは無駄ではないか」と本気で自問自答したんです。
でも毎日使うPCだからこそ、不安を抱えたまま使い続けること自体がストレスになると気づきました。
そこから「安心を買う決断は大げさではない」と考えるようになったのです。
自宅で格闘ゲームを配信していた日のことを思い出します。
わずか一瞬のカクつきで流れが断ち切られ、試合の行方が変わってしまいました。
その経験があって以来、私は「もう二度と同じ思いはしたくない」と心に誓いました。
仕事中にPCが固まり、大事なデータを失った苦い記憶とも重なります。
どうしても許せない感覚。
それを避けるための布石が64GBなのです。
車に例えるなら、EVの航続距離に似ていると思います。
近所だけの移動なら十分でも、長距離ドライブとなると「途中で充電できなかったらどうしよう」と不安になる。
64GBはその不安を解消してくれる存在。
ゲームだけなら32GBで事足りますが、配信や動画編集、あるいはAIツールを動かすとなると、64GBの余裕がじわりと効いてきます。
つまり安心のための選択です。
そして、悩みに悩んだ末に私は64GBを選びました。
BTOのカスタマイズ画面で何度もマウスを止め、「これで後悔しないか?」と自分に問いかけた。
最後は「後で泣くより、今投資する方がいい」という気持ちが勝ちました。
数年先のゲームがますます描画負荷を高めるだろうと考えると、最初から余裕をもっておく方が結局は合理的だと判断できたのです。
実際に運用してみて「間違ってなかったな」と思える。
これはかなり大きな安心感です。
結局のところ、32GBか64GBかの答えは使い方に直結します。
Core Ultra7 265KのようなCPUをフルに活かすならメモリの強みは欠かせません。
長く満足できる環境を保つための投資として、64GBは理にかなっていると思います。
私は64GBを選びました。
後悔を避けたい気持ちが強かったのです。
それが、最終的に私がこの道を選んだ理由です。
単なる容量比較ではなく、自分の生活や使い方に沿って安心を得るための投資でした。
265K搭載PC搭載ゲーミングPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56AG


| 【ZEFT Z56AG スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H6 Flow White |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z57CM


| 【ZEFT Z57CM スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster MasterFrame 600 Silver |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ NZXT製 水冷CPUクーラー Kraken Plus 360 RGB White |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55EM


| 【ZEFT Z55EM スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | be quiet! SILENT BASE 802 Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel Z890 チップセット ASRock製 Z890 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 1000W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (アスロック製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55XY


| 【ZEFT Z55XY スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster HAF 700 EVO 特別仕様 |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel Z890 チップセット ASRock製 Z890 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 1000W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (アスロック製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55BY


| 【ZEFT Z55BY スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | LianLi O11D EVO RGB Black 特別仕様 |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel Z890 チップセット ASRock製 Z890 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 1300W 80Plus PLATINUM認証 電源ユニット (ASRock製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
Gen5 SSDは本当に必要?コスパならGen4もあり
特に最近ではGen5モデルの登場で心が揺さぶられる場面が増えました。
ただ、私自身の経験から言わせてもらえば、今のところゲーム用途に関してはGen4で十分だと考えています。
ロード時間がちょっと短くなったところで、プレイそのものの楽しさや没入感は変わらない。
確かにGen5 SSDのスペック表を眺める時間には不思議な高揚感がありました。
14,000MB/sを超える読み込み速度なんて「すごいなぁ」とつい声が出そうになるほどです。
数字の迫力って人を魅了しますよね。
でも冷静になると、今の自分のゲーム環境でそれがどれだけの違いを生むのかと問われれば答えは微妙なんです。
憧れと現実。
結局そこに落ち着くのだと思います。
一番厄介だったのは発熱でした。
Gen5を試したとき、ヒートシンクの大きさや熱のこもり方に少しうんざりしたんです。
ケース内のエアフローを調整しきれず、GPUと干渉しそうになったときは本当に焦りました。
冷や汗ものでしたね。
そうなるとGen4は安心できる存在です。
熱もそこまで気にしなくていいですし、価格は落ち着いていて2TBでも手を出しやすい。
堅実に使える、というのはやっぱり大きな魅力です。
私も「どうせなら最新で固めたい」と思った瞬間が何度もあります。
Gen5を選んでみたくなる衝動。
まるで誰かが新しいスマホを手にした時のあの誇らしげな笑顔を見たときのように、「最先端を持つ優越感」に心が揺れるんです。
ただ、その気持ちはよく分かるものの、日常的な利便性や実用面とは必ずしも結びつかない。
むしろ「これは自己満足で終わる買い物にならないか」と自戒する場面もありました。
私が最終的に辿り着いた基準は「実際の用途と結びつくかどうか」です。
動画編集や3DCG制作などの用途ならGen5の恩恵は大きいでしょう。
数秒の短縮でも、それが積み重なれば圧倒的な効率差になります。
ただ私のメインはゲーム。
そこで必要とされる性能はGen4で十分に満たせる。
実際、WDやCrucialのGen4 SSDで構成しても不満はなく、むしろ浮いた予算をグラフィックボードに回せたことでプレイ環境はずっと快適になりました。
ぶっちゃけ、この方が断然楽しかったんです。
SSDの選び方は性能だけでなく、全体のバランスに直結します。
CPUをCore Ultra7シリーズあたりにしても、SSDに予算をつぎ込むよりGPUやメモリに力を入れる方が使っていて快適性に直結します。
ストレージの差が生み出す快適さはあくまで最後の数%。
それより、どんなゲームをどんな風に楽しみたいのかを突き詰めて考える方が大事です。
40代になってようやく気付いたことですが、見栄よりも効率の方がずっと満足度につながる。
そういうものなんです。
じゃあどう選ぶべきか。
その上で、もし気持ちのどこかで「どうしても最先端を試してみたい」と思ったときにはGen5を追加で導入すればいい。
最初から全部を最新で固める必要はなく、遊び心を満たしたくなったときにピンポイントで取り入れる。
これが一番無理のないやり方だと思っています。
2025年の今、Gen5 SSDはまだ成熟しきった安心感より、チャレンジや趣味性に近い領域の製品です。
だからこそ、背伸びしない方が後悔が少ないと私は確信しています。
安心できる選択。
堅実さに支えられる満足感。
私はそこにこそ本当の価値があると感じています。
最新技術に翻弄されるより、自分にとって必要な性能を見極め、それを冷静に選び取ること。
それさえ忘れなければ、ゲーミングPCの構成は間違いなく満足度の高いものになります。
CPUクーラーは水冷が必須か、それとも空冷で十分か
Core Ultra7 265Kを搭載したゲーミングPCを組むとき、私は空冷で十分だと確信しています。
なぜなら日常的な用途において大半の人が求めているのは「強烈に冷えること」よりも「安定して静かに動いてくれること」だからです。
高負荷環境で長時間ベンチマークを回すことが仕事でない限り、正直なところ水冷の性能を持て余してしまう場面が多いのではないでしょうか。
私自身、実際の作業やゲームプレイを通じて感じた安心感こそが答えだと思っています。
若い頃を思い返すと、私は一度だけフルカスタム水冷に挑戦したことがあります。
性能を追求したかったのと、ケース内部を光らせて自己満足を得たかったからです。
その時の高揚感は今も覚えています。
しかし年月が経つにつれ、ポンプ音に耳を澄ませて気になったり、液漏れが心配で深夜にふと考え込んでしまったり、そういう小さな負担が積み重なっていたことに気づいたのです。
正直めんどうでしたね。
一方で、ここ半年メインで使っているのは大型の空冷クーラーです。
これが実に心地よいのです。
ゲームをしていても温度は70度台を安定して維持し、ファンの音がほとんど気になりません。
夜中に遊んでいても家族から文句を言われないのは助かります。
PCがただ静かにそこにいてくれる、その安心感に何度も救われています。
静かっていいんです。
最近の空冷は一昔前のイメージとはまるで別物です。
ヒートパイプの効率も格段に上がり、フィンの形状にも工夫がされています。
大型の空冷を選べば水冷に迫る冷却力を発揮してくれるし、しかもメンテナンスはほとんど不要。
率直に言えば「ハイエンドCPU=水冷必須」という考え方は今では過去の話なのです。
特にCore Ultraシリーズは消費電力設計そのものが見直されており、ユーザーが無理をして冷却強化を考えなくても快適に使える形になっています。
だからこそ、過剰に走る必要はありません。
過去に小型ケースへ無理やり水冷ラジエーターを組み込み、配線にも苦しんで熱こもりを起こした経験があります。
今の私の構成は逆に大型の空冷を余裕をもって収められるケースを用意し、空気の流れを素直にしているので、本当に快適そのものです。
侮れないのです、ケース選び。
もちろん、水冷の魅力を分からないわけではありません。
見た目の華やかさは圧倒的です。
光るラジエーターやチューブがケースのガラスパネルを通して見えると、それだけで所有欲が満たされるものです。
それは確かに魅力。
若い頃と比べると、価値観がはっきり落ち着いてきたのを感じています。
大型の空冷クーラーであっても価格は水冷キットより安く、壊れるリスクや水漏れの心配もありません。
同じPCで仕事もゲームもこなしている私にとって、突発的なトラブルは本当に避けたいところです。
だからこそ空冷のシンプルさに救われています。
精神的に余裕を持って作業できる。
これが大きいんです。
これはやはり自分の使い方に尽きると思います。
性能を限界まで引き出して見た目のインパクトも楽しみたい方には水冷が正解になります。
Core Ultra7 265Kはピーキーな発熱を見せるほど攻撃的な性格ではないので、空冷でも余裕を持って扱えます。
私は自然にそちらを選びました。
つまり、Core Ultra7 265Kを搭載したPCなら空冷で十分に力を発揮できます。
重たい作業にも対応でき、夜の静けさの中で安心してゲームをプレイすることも可能なのです。
水冷に振り回されることもなく、日常を支えてくれる。
最適な選択肢は人によって変わりますが、私にとっての答えは明確です。
空冷こそがちょうどいい解答。
Core Ultra7 265K 搭載PCはBTOが賢明か、それとも自作か
昔は部品を探して自作することそのものが楽しくて、その達成感に酔ったものでした。
ただ、40代になった今は考え方が変わりました。
仕事も家庭も待ってくれませんし、少しのトラブルに貴重な時間を奪われるのは本当に厳しい。
だから今の私にとっては、動作検証や部品の相性チェックをすべて済ませた安定した一台を手にすることこそが最大の安心につながっているのです。
BTOの魅力のひとつは、部品同士の調和をメーカーが最初からきちんと確認してくれている点にあると思います。
例えば最新のCore Ultra7 265Kを搭載する場合、高性能パーツを単純に組み合わせただけでは本当の力が発揮できません。
電源の供給設計や冷却機構も全体のバランスを左右する大事な要素であり、それを自分ひとりで突き詰めるのはなかなか骨の折れる作業です。
私は過去に高発熱のSSDを軽く考えて組み込んだ結果、作業中に熱暴走で何度もシステムが落ちるという苦い経験がありました。
夜中に再起動を繰り返し、原因を突き止めるまで途方に暮れたあの気分は二度と味わいたくありません。
やっぱりすぐ使える一台が欲しい。
もちろん自作にしかない楽しさも理解しています。
ケースを開け、ひとつひとつの部品をはめ込み、最後に電源ボタンを押してファンの光が一斉に輝く瞬間には、少し誇らしい気持ちになる。
あれは忘れられません。
でもその反面、翌朝になって全く電源が入らなくなったパソコンを前にパネルを外し、ケーブルを点検し、再び組み直すあの絶望感も強烈に残っています。
正直に言えば「またかよ」と呟きたくなる瞬間でした。
だから今は安定性を優先するしかないのです。
費用面の現実も見逃せません。
BTOはGPUの価格に強さが出ます。
たとえば単体でRTX 5070クラスを買おうとすると結構高いのに、BTO構成に組み込むと驚くほど抑えられることが多い。
これは大手ショップが持つ仕入れ力や交渉力の違いです。
そのうえ保証が一本化されることも大きい。
これが地味にきつい。
時間も気力もごっそり削られる。
私は一度、自作でRTX 9070XTを導入しようとして痛い目を見ました。
映像が乱れ、最初はマザーボードを疑い、次にメモリを交換し、それでも解決せず数日間モヤモヤを抱えました。
ようやくGPUの初期不良だとわかったのは相当後のこと。
それなのに交換までさらに数週間。
休日をサポート窓口探しに費やし、手元には動かないPCが残るだけで、本当にやるせなかった。
あの時間を思い出すと今でも胃が重くなります。
だからこそ言い切れる。
サポート体制、ここにこそBTOの強みがあるのです。
ただし自作の意味が失われたわけではありません。
長期的な視点に立てばむしろ自作の方が選択肢は広がります。
未来志向のゲーマーや調整そのものに喜びを見出す人には、窮屈に感じる場面もきっとあるでしょう。
「自分だけの一台」を作る快感はやはり自作ならではです。
だからすべてを否定する気はありません。
趣味なんですから。
それでも、今のBTO製品の完成度は驚くほど高まっています。
Core Ultra7 265Kを搭載しても空冷で問題なく安定動作する冷却能力、DDR5や高速SSDとの相性検証済みの構成、さらには流行のピラーレスケースまで取り入れてモダンな外観に仕上がっている。
細部まで配慮されこうした要素が標準的に組み込まれるようになった現実には、本当に「時代が変わったな」と感じます。
昔のように「BTOは妥協の選択肢」とはいえません。
むしろ最短距離で完成度の高いPCを得られる手段になったと断言できます。
思い返せば若い頃の私は、「自作こそ正義」と思っていました。
求人誌やパーツ雑誌を手に秋葉原を歩き回り、どの組み合わせが最も将来性とコストのバランスを取れるか真剣に悩んでいた。
時には深夜まで半田ごてを握りしめることさえありました。
その頃はそれで楽しかったし、時間を費やすこと自体が財産だったのです。
生活と仕事の重みがあり、趣味の時間は限られています。
だからこそ、少なくともゲーミングPCに関しては私は迷わずBTOを選びます。
最終的な答えは明らかです。
Core Ultra7 265Kを搭載したゲーミングPCを買うなら、現代においてはBTOが最も実用的で安心できる選択です。
自作は趣味や知識欲を満たすために残しておき、本当に必要なマシンを手にする場面ではBTOに任せる。
これが私なりの折り合いの付け方だと思っています。
効率か、時間か。
答えはシンプルでした。
私にとって今大事なのは、家族や仕事、趣味をちゃんと両立させながら安心してPCを楽しめること。
だからこれからもきっと、私はBTOを選ぶでしょう。
信頼性。
人気PCゲームタイトル一覧
| ゲームタイトル | 発売日 | 推奨スペック | 公式 URL |
Steam URL |
|---|---|---|---|---|
| Street Fighter 6 / ストリートファイター6 | 2023/06/02 | プロセッサー: Core i7 8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: RTX2070 / Radeon RX 5700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter Wilds
/ モンスターハンターワイルズ |
2025/02/28 | プロセッサー:Core i5-11600K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce RTX 2070/ RTX 4060 / Radeon RX 6700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Apex Legends
/ エーペックスレジェンズ |
2020/11/05 | プロセッサー: Ryzen 5 / Core i5
グラフィック: Radeon R9 290/ GeForce GTX 970 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| ロマンシング サガ2
リベンジオブザセブン |
2024/10/25 | プロセッサー: Core i5-6400 / Ryzen 5 1400
グラフィック:GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| 黒神話:悟空 | 2024/08/20 | プロセッサー: Core i7-9700 / Ryzen 5 5500
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700 XT / Arc A750 |
公式 | steam |
| メタファー:リファンタジオ | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i5-7600 / Ryzen 5 2600
グラフィック:GeForce GTX 970 / Radeon RX 480 / Arc A380 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Call of Duty: Black Ops 6 | 2024/10/25 | プロセッサー:Core i7-6700K / Ryzen 5 1600X
グラフィック: GeForce RTX 3060 / GTX 1080Ti / Radeon RX 6600XT メモリー: 12 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンボール Sparking! ZERO | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i7-9700K / Ryzen 5 3600
グラフィック:GeForce RTX 2060 / Radeon RX Vega 64 メモリ: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE | 2024/06/21 | プロセッサー: Core i7-8700K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce GTX 1070 / RADEON RX VEGA 56 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ファイナルファンタジーXIV
黄金のレガシー |
2024/07/02 | プロセッサー: Core i7-9700
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Cities: Skylines II | 2023/10/25 | プロセッサー:Core i5-12600K / Ryzen 7 5800X
グラフィック: GeForce RTX 3080 | RadeonRX 6800 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンズドグマ 2 | 2024/03/21 | プロセッサー: Core i7-10700 / Ryzen 5 3600X
グラフィック GeForce RTX 2080 / Radeon RX 6700 メモリー: 16 GB |
公式 | steam |
| サイバーパンク2077:仮初めの自由 | 2023/09/26 | プロセッサー: Core i7-12700 / Ryzen 7 7800X3D
グラフィック: GeForce RTX 2060 SUPER / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ホグワーツ・レガシー | 2023/02/11 | プロセッサー: Core i7-8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: GeForce 1080 Ti / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| TEKKEN 8 / 鉄拳8 | 2024/01/26 | プロセッサー: Core i7-7700K / Ryzen 5 2600
グラフィック: GeForce RTX 2070/ Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Palworld / パルワールド | 2024/01/19 | プロセッサー: Core i9-9900K
グラフィック: GeForce RTX 2070 メモリー: 32 GB RAM |
公式 | steam |
| オーバーウォッチ 2 | 2023/08/11 | プロセッサー:Core i7 / Ryzen 5
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 6400 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter RISE: Sunbreak
/ モンスターハンターライズ:サンブレイク |
2022/01/13 | プロセッサー:Core i5-4460 / AMD FX-8300
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| BIOHAZARD RE:4 | 2023/03/24 | プロセッサー: Ryzen 5 3600 / Core i7 8700
グラフィック: Radeon RX 5700 / GeForce GTX 1070 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| デッドバイデイライト | 2016/06/15 | プロセッサー: Core i3 / AMD FX-8300
グラフィック: 4GB VRAM以上 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Forza Horizon 5 | 2021/11/09 | プロセッサー: Core i5-8400 / Ryzen 5 1500X
グラフィック: GTX 1070 / Radeon RX 590 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |