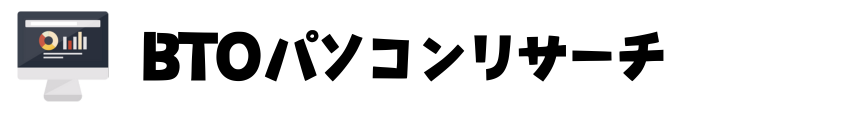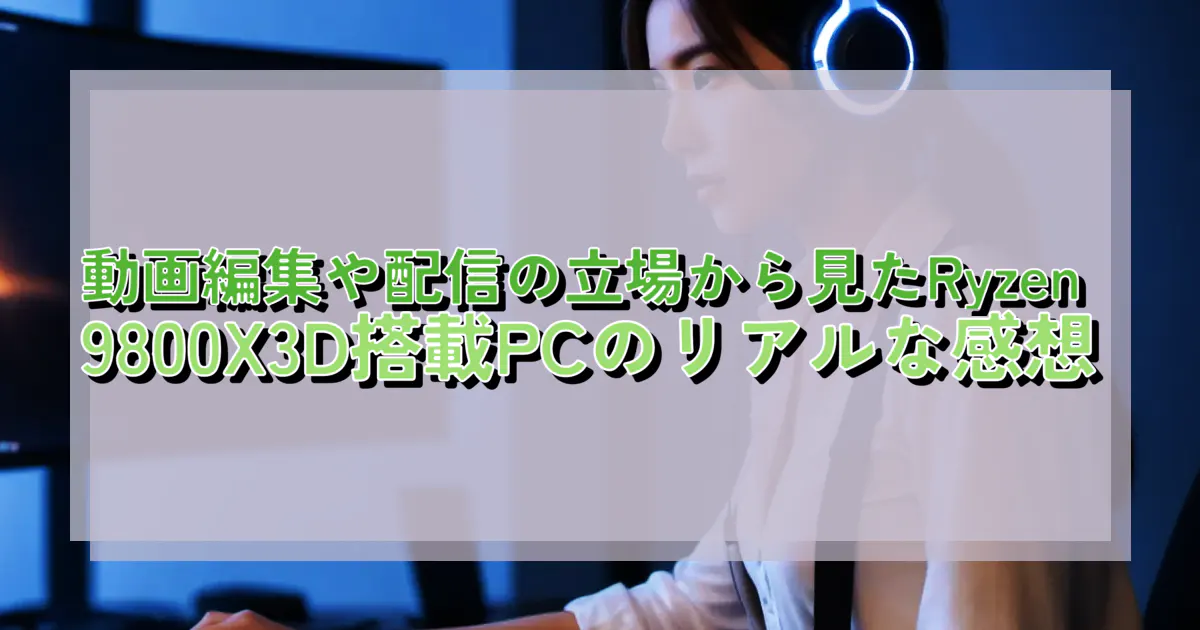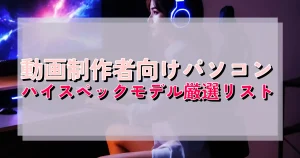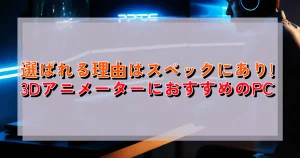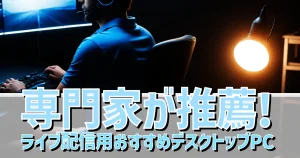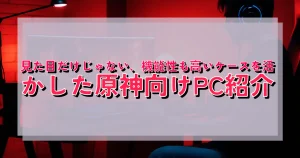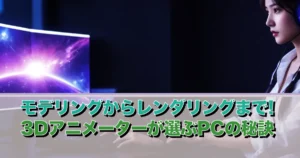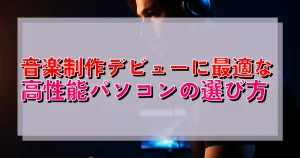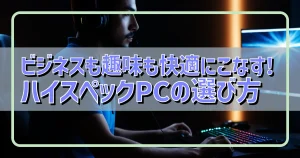Ryzen 9800X3D 搭載PCで検証する動画編集の実力

4K編集時のCPU使用率と作業中の安定性を観察
実際に使ってみて改めて感じたのは、Ryzen 9800X3Dは動画編集において極めて安心できる相棒になるということです。
数値だけを追いかけるよりも、実際の現場で試したときの体験こそがすべてで、PremiereやDaVinci Resolveで4K編集を進めても引っかかりを感じない。
安心して進められる、この感覚が何より大切だと実感しました。
特に記憶に残っているのは、10bit 4:2:2の重い素材を複数走らせてもCPU使用率が6割程度で収まっていた場面です。
旧世代のX3Dを使っていたときは7割を超えることも多々あり、それこそ作業中に「途中で止まったらどうしよう」と手が止まる瞬間もありました。
ですが今回は違う。
プレビューにコマ落ちがなく、音のズレも起きない。
操作を積み重ねても不安が生じない余裕があるんです。
正直なところ、これがどれほど業務の心理的負担を軽減するかは、実際にやっている人にしか分からないと思います。
エフェクトを加えてCPUに負荷をかけても本当に余力がある。
これなら締め切り間際のギリギリの場面でも「これ以上は危ない」という不安を抱かずに済みます。
精神的な支え。
まさにそんな存在です。
もちろん不満がないわけではありません。
長時間レンダリングをかけると一時的に温度が80度近くまで上昇することがありました。
そのときは「やはり限界近くで頑張っているな」とCPUの息遣いを感じたものです。
ただし高性能空冷クーラーを組み合わせれば十分対処可能で、温度に怯える必要はほとんどありませんでした。
これが地味ながらも実用上の大きな安心につながります。
さらに重要だと思ったのはGPUとの相性です。
レンダリング効率も高く、CPUとGPUが互いを補い合っている感じがする。
逆に下位のGPUを試した際にはCPUが持て余すような挙動をしてしまい、やはり全体のバランスを見極めることの大切さを改めて知りました。
動画編集においては部品単体で語るのではなく、システムとしてどう設計するかが真価を決めるのだと思います。
さて、余裕。
OBSで配信と編集を同時並行させてみても、音声も映像も滑らかに走り続けてくれました。
エンコードを裏で回しながらでも使用率は8割前後で抑え込まれ、まったく止まらない。
過去に同じような状況で配信映像がカクつき、冷や汗をかいた経験があるだけに、この安定感には思わず「ありがとう」と言いたくなるほどでした。
複数工程を平行して進められる安心感こそ、現場において最も価値のある支えになります。
もう一つ試したのは、小規模なプロジェクトを片方でレンダリングしながらもう一方を編集する作業です。
結果として、ほとんどトラブルもなく同時処理が走りました。
これなら現場で複数案件を抱えていても恐れずに同時進行できる、と強く感じました。
実際の業務に即した安定性。
これが大切なんです。
音の面も見逃せません。
空冷ファンがうなる場面はありましたが、それも制御が効いており気になるレベルではなかった。
私は以前に簡易水冷のトラブルを経験し、そのときは冷却液の漏れに青ざめたこともありました。
ですから長く安心して使える空冷への信頼は強いです。
9800X3Dであれば、大型の空冷クーラーを組み込めば十分に安定稼働が期待できる。
実際に業務に携わっている人ほど、この「安心して任せられる冷却」の価値に気づけるはずです。
さらに120fpsでのプレビューまで試しましたが、処理落ちの気配がまったくないことには驚きました。
GPUの恩恵があるとはいえ、CPU自体がしっかり追随できる力量を持っているという事実は大きな意味を持ちます。
動画編集で最も心を削られるのは「やりたいことなのに処理が遅れて作業が途切れる」こと。
そのストレスから解放してくれる存在だと、心から実感できました。
業務の現場では「速い」だけでは不十分で、「止まらない」ことが何より大切です。
このCPUはその確実性を提供してくれる。
だから私は胸を張って言えます。
このモデルを選ぶなら後悔はしない。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 42777 | 2466 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42532 | 2270 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 41569 | 2261 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 40867 | 2359 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38351 | 2079 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38276 | 2050 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37049 | 2357 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37049 | 2357 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35430 | 2198 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35290 | 2236 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33552 | 2209 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32699 | 2239 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32334 | 2103 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32224 | 2194 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29074 | 2041 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28365 | 2157 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28365 | 2157 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25293 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25293 | 2176 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 22944 | 2213 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 22932 | 2093 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20726 | 1860 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19385 | 1938 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17621 | 1817 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 15947 | 1779 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15194 | 1983 | 公式 | 価格 |
Premiere ProやDaVinci Resolveを動かしてみた印象
最初は正直、ゲーム向けだから編集にはそこまで役に立たないんじゃないかと疑っていたんです。
でも、その予想は見事に裏切られました。
Premiere Proでカット編集をしているときも、DaVinci Resolveでトランジションをかけるときも、とにかく操作の反応が軽やかで、作業リズムが途切れないんですよ。
サクサク感。
これが集中力を保ってくれる一番の理由でした。
タイムラインに複数のカメラ素材を並べた上で、裏で書き出しまで同時進行させてもカクつきが起こらないのには驚かされました。
その変化はわずかな違いに見えるかもしれませんが、一日中同じ作業をしていると疲労感が全然違うんです。
地味に効くんですよね、こういう部分が。
カラーグレーディングに関しても大きな差を感じました。
DaVinci Resolveで調整を繰り返すとき、GPU負荷が大きくなるとどうしてもCPUとの連携がボトルネックになりやすいのですが、このCPUではそうした窮屈さをほとんど意識せずに済みました。
AI系の機能も割と自然に走るので、これまでハードルに感じていた処理を「まあいけるだろう」と肩の力を抜いて扱える安心感がありました。
作業に余白が生まれるんです。
今回のテスト環境はメモリが64GB、ストレージはGen.4の2TB SSD。
普段よりも負荷が高い条件を想定して使ってみても、9600Mbpsクラスの高ビットレート素材をそのまま扱えてしまいました。
プロキシを毎回作らなくていいというだけで、どれほど楽になるか。
長時間の案件を扱う立場だからこそ、「無理をかけずに安定して動く」という安心感に大きな価値を感じます。
この手応えは数字以上の説得力がありました。
エンコードの処理速度も目に見えて上がっていました。
例えばPremiere ProでH.264の映像を書き出す場合、以前は10分程度の素材だと結構待たされる印象だったのですが、今では3割近く速く終わる。
これは作業時間を直接削ってくれる変化です。
待ち時間って、本当に集中力を奪うんです。
ストレスも減り、次のタスクに気持ちを切り替える余裕が生まれる。
数字で説明できる進化ですが、体感の方がずっと大きいものでした。
DaVinci ResolveでH.265書き出しを試したときも同じ印象を受けました。
冷却ファンが過去ほど激しく回らないんです。
以前は処理中の轟音にへきえきしていましたが、今は自然に処理が進んでしまう。
静かに完走してくれるだけで、これほど作業環境が快適になるのかと実感しました。
耳に刺さるノイズが少ないと、長時間向き合う40代の私にはありがたさしかありません。
これが毎日の積み重ねになると本当に大きな違いになります。
一般的にはRyzen 9800X3Dといえば「ゲーム用」という印象が先に立ちますが、それだけで判断するのはもったいないと思います。
確かにコア数を徹底的に求める人にはより上のRyzen 9 9950X3DのようなCPUが魅力的に映るかもしれません。
しかし私のように「遊びと仕事が一つの環境に同居している」という状況では、9800X3Dは実にちょうどいい落としどころにあります。
半端ではなく、本当にバランスしている。
これは評価に値するポイントだと私は思います。
気になる発熱についても触れておきます。
正直、空冷で十分対応できました。
ピーク温度でも危なっかしい印象はなく、ケースのエアフローをそこまで神経質に考える必要もありません。
水冷を導入する必要がないと断言できるのは嬉しい誤算でした。
電力効率も改善していて、電気代をどうしても意識する世代としては本当に助かります。
毎月の出費の中で小さな安心が積み重なる。
それが快適さにつながるのです。
配信テストでも優秀さを発揮しました。
OBSで4K配信をしながら、裏でDaVinci Resolveの書き出しを同時に走らせてもフレーム落ちが起きなかった。
これは大きな差です。
放送事故を気にせずに進行できる。
この余裕が精神的にどれほど楽か、配信経験者なら分かるはずです。
一連の体験を振り返って、私は「動画編集用として9800X3Dを検討外にするのは損だ」と確信しました。
もちろん専門性が突き抜けている分野の人には、もっと上のクラスが必要になることもあると思います。
しかし私のように仕事も遊びも配信もまとめてこなしたい人間には、このCPUはぴったりすぎるんです。
つまり、Ryzen 9800X3Dはゲーム用のレッテルを貼られがちな存在でありながら、Premiere ProやDaVinci Resolveでもしっかり力を発揮してくれるCPUでした。
編集も配信も遊びも一緒に楽しみたい。
そんなわがままなニーズにこそ応えるパートナー。
それがこのCPUだと私は思っています。
書き出し速度とメモリ容量の違いが作業効率に与える差
動画編集や配信の現場で本当に効果を実感するのは、CPUやGPUの数値そのものの高さではなく、書き出し速度とメモリ容量のかみ合い方だと私は感じています。
Ryzen 9800X3Dを中心に組んだマシンをしばらく使ってきましたが、最も心に残っているのは「作業の途中でイライラしなくなった」という点でした。
レンダリング時間が短縮したのもありがたいのですが、それ以上に、タイムラインにエフェクトを重ねても動作が止まらない。
この余裕があるだけで、気持ちの負担が減るのです。
その結果として効率が格段に上がり、自分の力を無駄なく発揮できる環境になったのです。
これは決して誇張ではありません。
書き出し速度に関しては、最新のPCIe Gen.4やGen.5対応SSDを導入しただけで、素材の読み込みからエクスポートまでの時間がまるで別物に変わりました。
以前は数分、下手をすると10分以上待っていた重たいプロジェクトが、今ではその半分ほどの時間で終了します。
納品の現場では数分の違いが命取りになることがあります。
まさに現場に直結する改善です。
メモリについても痛い経験をしてきました。
私は最初32GBで編集と配信の両立をしていたのですが、同時に複数アプリを開いただけで一気に重くなり、配信中に固まってしまったことがあったのです。
あの時の焦りは忘れられません。
本番中の冷や汗ほど嫌なものはない。
その出来事をきっかけに64GBへ移行したのですが、そこで感じた快適さは段違いでした。
安堵感がありましたね。
安心感。
今では64GBは保険ではなく前提条件だと思っています。
長尺の動画編集や配信と同時録画を進めるとき、メモリが潤沢であるかどうかで精神的な負担は大きく変わります。
「業務を止めないために投じる投資」というよりも、「仕事を存分に走らせるための基盤」です。
さらにCPUと書き出し速度のかみ合いも無視できません。
途切れない感覚でタスクが進んでいく。
それが編集者にとって何より大きい。
力強いCPU、速いSSD、そして余裕あるメモリ。
三位一体でようやく「仕事が止まらない環境」が完成します。
配信をしながら録画し、同時にその映像を編集するという無茶な試みもしましたが、Ryzen 9800X3Dを中心にした環境では、トラブルもなく動いてくれました。
過去の環境だったら確実に落ちただろう場面で、安定してくれたことには驚きました。
おかげで深夜に残業してやり直すこともなく、夜は家族と食事を囲めた。
これが本当にありがたいんです。
救われた気分。
ただし、誤解されたくないのは「ストレージやメモリの片方だけでは不十分」ということです。
SSDの性能数値が高くても、メモリが足りなければ結局は詰まる。
逆もまた同じ。
どちらか一方ではなく、両方の仕組みがそろって初めて快適さが実現される。
この単純でありながら見落とされがちな事実を、もっと多くの人に知ってほしいという想いがあります。
私はかつてCPUの性能値ばかりを追い、結果的に書き出し速度が遅く、納期を乱してしまった苦い経験をしました。
Ryzen 9800X3Dを本気で選ぶなら、最低でも32GB以上のメモリと十分な速度を持つSSDを組み合わせる。
これを欠いた構成では、「ストレスフリー」とは到底呼べません。
では、どこまで投資すべきか。
私が行き着いた答えはシンプルです。
この構成が最も安心して使えるバランスです。
書き出し速度とメモリ容量の両輪で生み出される余裕は、確実に納期に直結し、最終的な作品品質にも影響します。
迷うなら揃えること。
効率を最大化したいのなら、CPUの力を存分に引き出す周辺環境にきちんと手を入れる。
その姿勢が真に快適な作業環境につながるということを、私は自分の経験を通じてようやく理解しました。
振り返れば遠回りも多く、悔しい失敗もありました。
しかし今ははっきり言えます。
それが正解だと。
Ryzen 9800X3D 搭載PCで実際に配信してみたパフォーマンス
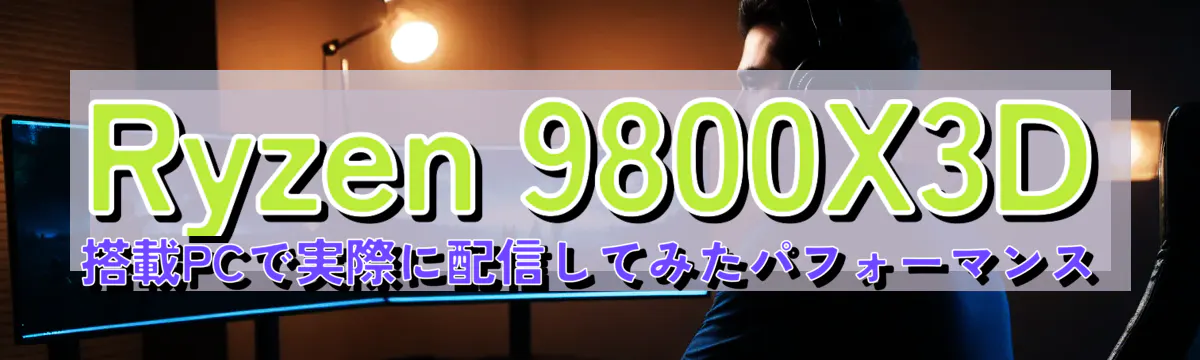
OBSで配信したときのフレーム維持と画質調整のしやすさ
こちら側がどんなに熱を込めて話していても、映像がカクついたりフレームが飛んでしまった瞬間に、相手の集中は途切れてしまう。
正直なところ、それは怖い。
だから私は配信環境を整えるとき、常に「途切れなく流れる」ことを最優先に考えてきました。
今回Ryzen 9800X3Dを導入して実際に長時間配信をしてみて、まず驚かされたのは余裕のある動作でした。
フレームも一定で、長時間維持できる。
私は正直、配信後に肩の力が抜けるほどホッとしましたよ。
やっぱり安心感って大事なんです。
エンコード方式を切り替えるときも思いましたが、このCPUは扱いやすい。
ソフトウェアエンコードにしても処理落ちで映像が乱れるようなことはなく、画質優先に振っても動きに余力を感じられる。
高負荷シーンが続いたときでも「まだ大丈夫かな」と心で思える余裕が残っているんです。
この精神的なゆとり、実際に使ってみないと分からない価値ですよ。
映像品質の面でもハッキリした効果がありました。
OBSでプリセットを一段重くしてもフレームが崩れずに動く。
その結果、リスナーは違和感なく楽しめるんです。
実際、GPUにRTX 5070Tiを組み合わせてみると、ゲーム側の描写も配信側の映像もどちらも乱れないという絶妙なバランスが出せました。
これは簡単にできることではない。
配信者として「両方諦めたくない」という気持ちを満たしてくれる環境は本当にありがたいです。
実際に触ってみると、大容量キャッシュの効果かな、と肌で納得しました。
ただし、当然ながら欲張れば熱問題は避けて通れない。
私も最初、水冷の導入を一瞬考えました。
しかし実際には、120Wクラスの消費電力でも最新ケースとしっかりした空冷クーラーで十分対応できる。
冷却環境を手を抜かずに整えれば安定性は崩れないというのは実感としてあります。
画質面でさらに助かるのは、ビットレート制限を受けながらも細部が破綻しない点です。
最近のゲームはとにかく派手で、爆発や群衆で一気に負荷が跳ね上がる場面も多い。
でもRyzen 9800X3Dだと、不思議なほど映像が潰れません。
だから「これなら思い切って見せられるな」と、つい口に出してしまったほどです。
自信につながる。
一方で、気になる点もないわけではありません。
正直に言うと、ややGPU依存の側面が見えるんです。
エンコードを更に突き詰めていくとCPUだけではどうにもならない場面が出てきて、結局はGPUの世代や性能が画質の伸び代を左右してしまう。
そういうとき「ここが限界か」と思う瞬間は確かにある。
ただ、見方を変えるとCPUが安定しているおかげでGPUに集中して調整できるんです。
負荷範囲が分かりやすいというのは大きなメリットです。
あらためて全体を振り返ると、このCPUを中心にした環境は配信に必要な安定感と画質調整のしやすさを高水準で両立してくれる。
私自身が配信を職業として続けている中で、率直に「これなら文句は少ない」と思いました。
ストレス要因が減り、本来の仕事に集中できるようになります。
最終的に言えることは、このRyzen 9800X3Dは単なるスペックの高さではなく、現場で感じる安心感や運用の快適さこそが真価なんだということです。
それは数値の比較で伝えにくい部分ですが、実際に使用してみると心の負担が軽くなる。
結局それが、このCPUの答えなんでしょうね。
頼もしさ。
また安心感。
長時間の配信を経験した身として、こうして落ち着いて書けるのもあの余裕をくれた環境のおかげだと実感しています。
GPUエンコードとCPUエンコードを切り替えて試した結果
配信環境を整えていく中で、私が一番強く意識したのは「途切れない映像の安心感」でした。
人によっては多少画質が荒くても気にならないかもしれませんが、カクつきや停止は一瞬で没入感を壊してしまう。
視聴者の体験を守る意味で、滑らかに流れることそのものが大前提になると痛感しました。
だからこそ私は、GPUエンコードを配信の中心に据えると決めたのです。
その瞬間の感覚は、数字やグラフでは説明できず、完全に「肌でわかる安定感」だったのです。
ほっとするような安心感。
これ以上ないと思いましたね。
ただ、ここで新しい発見もありました。
人物の髪の毛が一本一本くっきりと見える鮮明さを手にした時は正直「ここまで変わるのか」と感嘆しました。
ほんの少し鳥肌が立ったくらいです。
そこで私は一度立ち止まって、配信と録画を完全に分けて考えるというアプローチを試しました。
配信ではGPUに任せて安定を確保し、録画についてはCPUを使って最大限の画質を残す。
この二本立ての使い分けを実際に試したところ、配信は止まることなく続き、録画映像は自分で見返しても惚れ惚れするほどの鮮明さでした。
そのとき「これがひとつ上のレベルの運用だ」と確信したのです。
特にCPUエンコードで保存した動画の鮮やかさには驚きがありました。
たとえるなら最新スマホのカメラでAI補正をかけた写真の滑らかさや自然さに近いもので、見ていて気持ちよくなる映像でした。
単なる記録ではなく「作品」とも言える質感。
配信は生ものですが、映像が高画質で残るという事実は大きな財産なのだと強く思ったのです。
とはいえ環境によっては都合よくはいきません。
オープンワールド系の重量級タイトルを遊びながらCPUエンコードを走らせると、フレームレートがジリジリ下がってプレイ自体に違和感が出る。
楽しむどころか、途中で「これは無理だな」と感じてしまう瞬間もありました。
一方で軽量なゲームであれば余裕を持ってCPUを走らせられるため、画質優先の配信すら実現できたのです。
やはり9800X3Dの力があるからこそ、この柔軟な選択肢が見えてくるのだと分かりました。
ここで強調したいのは「どちらが正解か」という問いそのものが少しズレているということです。
配信と録画の両方を高めたいのか、それとも安定第一で進めたいのか。
その答えは状況によって変わるものであり、私にとってはGPUエンコードとCPUエンコードを使い分けることが最適解となりました。
GPUで安定を、CPUで美しさを。
柔軟性は力です。
私の中では整理はとてもシンプルになりました。
配信はGPU、録画はCPU。
これが今の私にとってのベストな組み合わせです。
もちろんGPUだけに任せて手軽に済ませる方法も悪くありません。
むしろ多くの人がそれを選ぶでしょう。
でも、せっかく9800X3Dのような性能を持つCPUを手にしているのであれば、眠らせておくのはもったいないと感じました。
実際に試してみてその潜在力を確かめられたことを、私は今少しだけ誇らしく思っているのです。
贅沢な二刀流。
そんなイメージです。
GPUで安定感のある土台を築き、CPUで芸術的な描写を刻む。
両方を操れるだけで、「配信を楽しむ」という行為がまるで豊かさを増したかのように感じます。
9800X3Dが示してくれたのは、何かひとつに決めつけるのではなく、柔軟に動ける自由さでした。
その自由を味わえただけでも、環境を構築する苦労は十分に報われたと思っています。
最後に私なりのひとことを添えます。
迷ったときはGPUを選ぶ。
それが配信の世界で生き抜くための実践的な知恵でした。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48367 | 101934 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 31937 | 78073 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 29952 | 66760 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 29876 | 73425 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 26983 | 68929 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26330 | 60239 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 21804 | 56800 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19787 | 50483 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16451 | 39372 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 15888 | 38200 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15751 | 37977 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14542 | 34920 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13652 | 30859 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13115 | 32361 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10750 | 31742 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10580 | 28585 | 115W | 公式 | 価格 |
9800X3D搭載PC搭載ゲーミングPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60SU

| 【ZEFT R60SU スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60GY

| 【ZEFT R60GY スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9070XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| キャプチャカード | キャプチャボード AVERMEDIA Live Gamer 4K GC575 |
| ケース | NZXT H9 FLOW RGB ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II White |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61BO

| 【ZEFT R61BO スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61F

| 【ZEFT R61F スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60RF

| 【ZEFT R60RF スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
配信しながら他のアプリを動かすときの使い勝手
配信しながら同時に別の作業を快適にこなせるかどうか。
これは私にとって長年の課題でした。
Ryzen 9800X3Dを導入してから、ようやくその悩みに終止符を打てたと言えると思います。
正直なところ、以前のCPUではブラウザを開いて調べものをしつつ動画編集ソフトを動かし、さらに配信までしてしまうと途端に処理が止まってしまうことが多かったのです。
そのたびに配信の画面が固まり、コメント欄に「止まってますよ」と書かれると冷や汗をかきながらリカバリーを試みていました。
もうあの気まずさは二度と味わいたくないと思っていたのですが、この9800X3Dにしてからはそうした恐怖とは無縁になりました。
本当に助かりました。
実際にゲーム配信をしているとき、ゲームの処理とエンコード作業が同時並行するためCPUの負担は相当大きいものです。
それにもかかわらず、この9800X3Dは落ち着いて処理を続けてくれる印象があります。
私は配信しながら別のウィンドウで素材探しを行い、さらに音声編集アプリまで立ち上げて試しましたが、途切れや遅延は一切気にならないレベルでした。
画面フレームの安定感。
音割れのない音声。
そうした小さな積み重ねが配信者の安心につながるのだと改めて感じました。
とはいえ、CPU単体で全てが解決するわけではありません。
GPUの支えは欠かせないのです。
私はGeForce RTX5070Tiを組み合わせていますが、これが思った以上に力を発揮してくれました。
率直にいえば拍子抜けしたほどですし、コストを考えても非常にバランスが良いと感じています。
やっと納得のいく組み合わせに出会えたという手応えがあるのです。
また、マルチタスク環境で大事になってくるのがメモリです。
私はDDR5?5600の32GB構成で試しましたが、正直なところこれでかなり余裕がありました。
もちろん64GBあればなお安心です。
過去には「あと少し容量が足りれば」と不安になることが多かったのですが、今ではその nagging な心配がなくなり、ようやくメモリ不足に怯えずに取り組めるようになったことに心からほっとしています。
それでも不安がゼロになるわけではなく、私が配信環境を考える時に必ず頭をよぎるのが熱処理の問題です。
そこで今回はDEEPCOOLの大型空冷クーラーを用意しました。
結果として三時間以上連続で配信しても動作は安定し、クロックダウンの兆候すらなく稼働し続けてくれました。
その安心感には本当に救われました。
昔は汗をかきながら冷や冷や使っていましたが、今は肩の力を抜いて配信に集中できるのです。
「これだよ、求めてたのは」と思いました。
ストレージについてはGen.4 SSDを選びました。
もちろん最新のGen.5も気になるのですが、私の目にはまだ発熱と価格のバランスが不安要素に映ります。
その点、Gen.4の2TB構成であれば複数GB級の動画ファイルも軽快に扱え、配信後にすぐ確認や整理をする際にもストレスをほとんど感じませんでした。
配信ツールを止めずに並行処理することを考えると、今の自分にはこの選択で正解だったのだろうと素直に思っています。
十分。
さらにケース選びも意外と重要でした。
私は側面がガラスパネルのシンプルなケースを選びましたが、その理由はただ一点で冷却効率を優先させたかったからです。
結果的には部屋の雰囲気にも馴染み、内部の明るさも程よく保たれる理想的な環境になりました。
安易に見た目で選ぶのではなく、冷却を第一に置いた決断が自分にとって正しかったのだと感じています。
エアフローを侮ると後で苦労しますからね。
この環境にしてからは、ゲーム配信の最中であっても同時に動画編集を進められるようになりましたし、配信画面を切り替えても動作のもたつきがないので、「あれ、もうここまで進んだのか」と驚くほどスムーズに作業が運ぶようになりました。
例えばこれまでなら一日のうちに区切りごとに進めざるを得なかったプロセスが、一気にまとめて片付く。
時間の制約を意識せずに取り組めるという解放感は思った以上に大きく、配信も編集も含めて自分の仕事の流れが劇的に変わりました。
この効率化が与える心理的余裕が何より価値ある成果だったと思います。
最終的に私が伝えたいのは、Ryzen 9800X3Dは配信をしながら他のタスクも平行して進めたいと考えている人にとって、非常に信頼できる選択肢だということです。
GPUやメモリ、ストレージときちんと組み合わせれば、今までのような「どこで限界が来るかな」と悩む必要もなく、落ち着いて作業に向き合えます。
私は実際に使ってみて「これしかない」と思ったくらいです。
配信やマルチタスクに頭を抱えている人にとって、このCPUは間違いなく日々のストレスを減らしてくれる味方になるでしょう。
安心できる相棒。
ゲーマーとして体感したRyzen 9800X3D 搭載PCの実力
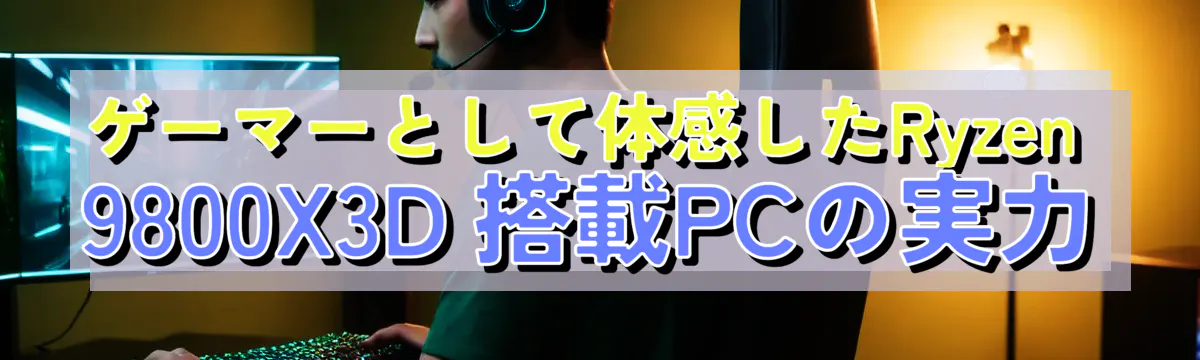
最新RTX 50シリーズGPUとの組み合わせで感じた変化
Ryzen 9800X3DとRTX 50シリーズを組み合わせた環境を自宅で使い始めてみて、率直に言えば「長く安心して付き合える構成だ」と強く感じました。
これまでグラフィックボードの性能ばかりが先に進み、肝心のCPU側が追いつかず、せっかくの映像が時折カクついたり配信ソフトが重荷になったりすることが多かったのですが、今回はその不満が嘘のように消えました。
むしろ、一段格上の安定感が常に後ろ盾についていてくれるような感覚で、思わず笑みがこぼれてしまったほどです。
特に印象的だったのはRTX 5070Tiを組み合わせたときの動作でした。
4K解像度でゲームを回してもCPU側の処理に詰まりが見えず、スクロールやカメラ移動があまりにも滑らかに更新されるため「これは本当に自分の環境なのか」と思わず首をひねってしまったくらいです。
今までCPUとGPUはどこかで小競り合いをしているように感じていましたが、今回はその関係が見事に整い、互いに信頼し合って役割を果たしている雰囲気を感じました。
正直、頼もしすぎる。
私はこれまで何度もPCを組み替えてきた中で、CPUとGPUのバランスが崩れると途端に快適さが損なわれることを身にしみて体験してきました。
例えばフレームレートの数字が高めに出ているのに、実際には映像がなぜか引っかかるとか、ライブ配信を始めると急にソフト全体が重たくなるとか。
ところが今回の構成ではRyzen 9800X3Dのキャッシュ設計が効いているのか、AIを利用した処理でも待ち時間をほとんど感じません。
動画を編集しつつ、裏でゲームを立ち上げるような雑な使い方をしても余裕が残っている手応えに正直驚かされました。
まさに大人の余裕。
さらにDLSS 4やニューラルシェーダーといった最新の技術が加わることで、映像の美しさと実際の操作感の両立が見事に成り立っています。
数値的にはフレーム生成で大きな改善が見えるのですが、その裏できっちりRyzen側がさりげなく制御を効かせているように思えました。
まるで現場を冷静に取りまとめる頼れる上司のようで、自然と安心感がにじみます。
こういうバランスの良さは机上のスペック比較では伝わらない部分です。
想像以上の快適さを感じたのはRTX 5090を組み合わせて8Kでレンダリングをかけたときです。
画面は目を奪うほど鮮やかでありながら動作は安定しており、まるで業務用の高価なワークステーションを自宅に持ち込んだかのような錯覚さえしました。
普段使いのPCという枠を超えてしまった充実感があり、「これ以上いったい何を望むんだ」と声に出した自分に笑いました。
もちろん課題もあります。
RTX 50シリーズが抱える消費電力や発熱の問題は看過できません。
私も最初に構成を試したとき、電源容量がギリギリで冷や汗をかいたことがあります。
パーツ選定の段階でそこを軽視すると宝の持ち腐れになります。
せっかくの性能を引き出すには堅実な電源ユニットと冷却設計が必須で、ここを見落とすと後悔する羽目になるでしょう。
油断大敵です。
しばらく長時間利用を重ねてみると、CPUとGPUがきちんと協調しながら動いているのが手に取るように分かりました。
動画編集ソフトでAI処理をばんばん適用しても待ち時間が極端に短く済み、バックグラウンドで複数アプリを同時に動かしてもCPU使用率が驚くほど低いのです。
これは9800X3Dの広大なキャッシュが効いているのに加え、RTX 50シリーズ側の演算支援がうまく噛み合っているからだと思います。
作業環境が崩れないのは本当にありがたい。
GPUの力を本気で引き出すには、土台となるCPUがしっかり支えている必要があります。
今回の組み合わせで痛感したのは、Ryzen 9800X3DがあるからこそRTX 50シリーズの能力が解放されるという事実です。
この前提を軽んじればせっかくの投資を無駄にしてしまいかねません。
それを学んだのは大きな収穫でした。
私の結論はシンプルです。
もちろん他の選択肢も少なくありませんが、長期的に見ても不満を感じず、仕事にも遊びにも腰を据えて取り組みたいなら、この組み合わせが頭一つ抜けていると感じています。
正直なところ、私はこの構成に触れてようやく自分のPC環境が完成したと胸を張れる心境になれました。
静かな満足感に包まれています。
長く寄り添える相棒です。
単に性能が高いだけではなく、余計な心配なく付き合えること。
普段の仕事をしっかり支え、余暇の時間を思いきり楽しませてくれる。
安心できる環境です。
4K解像度で実際に測れたフレームレート
4K環境での実際のプレイを重ねてきた今、私の中で一つはっきりしていることがあります。
それは、Ryzen 9800X3Dが現行世代の中で最も頼りになるCPUのひとつだと実感している、ということです。
これまでいくつものX3D世代のCPUを試してきましたが、今回ほど「CPUに助けられている」と素直に思えたことはありません。
特に4Kウルトラ設定で100fps前後を安定的に維持できるシーンが増えたことで、従来感じていたCPU負荷による映像の乱れが大幅に抑えられました。
思わず「これは本当にすごいな」と口に出してしまった瞬間すらあります。
最新のAAAタイトルではGPUの性能だけで快適さが決まると思われがちですが、そう単純ではありません。
CPUの処理が追いつかないとカクつきやフレームの乱れが顔を出してきます。
しかしRyzen 9800X3DとRTX 5070Tiを組み合わせた環境では、4Kの厳しい条件下でもフレームの揺れ幅が驚くほど小さいのです。
80fps台に僅かに落ち込む程度で、映像が途切れるような不安感はほとんどなくなりました。
そのおかげで長時間のプレイでも集中力が途切れず、時間を忘れて遊んでしまうんです。
まさに快適そのもの。
キャッシュの恩恵も強く感じました。
森の中や都市部のように処理が複雑になる場面では、これまでなら必ず目にした一瞬のコマ落ちがほぼ解消されています。
GPUをしっかりとCPUが支えている印象で、「ようやくここまで来たか」と心の底から思ったものです。
感慨深い瞬間。
しかも負荷がピークに達する場面では120fps近く跳ね上がる瞬間もあり、正直なところ「ここまで安定するのか」と驚きを隠せませんでした。
これはGPUの進化だけでは説明がつかず、CPU側のメモリアクセス効率が大きく作用しているのだろうと感じます。
特に長時間プレイでは数字の高さよりも「突発的なカクつきが消えている」ことのほうが体感的には大きな価値を持ちます。
ほんの一瞬の途切れでも気持ちが冷めてしまうのがゲームの世界ですが、その違和感がほとんどなくなったのは大きいです。
安心感につながりました。
一方で競技性の高いFPSやシューターにおいても変化を感じました。
GPU性能の比重が大きいのは当然ですが、CPUの遅延が減少したおかげで入力の反映が即座に行われるようになったのです。
マウスを動かしたりキーを叩いた瞬間に画面が応じてくれる感覚は、プレイヤーにとって価値があるという言葉では足りません。
シミュレーション系のゲームでもキャッシュ構造が真価を発揮し、フレーム単位で処理の応答が改善されました。
このなめらかさはまさに病みつきになります。
縁の下の力持ち。
例えば8K解像度を狙うとさすがにGPUの要求が極端に膨らみ、CPUだけでの支えは難しいです。
しかし4K環境に限れば、Ryzen 9800X3Dの安定感はゆるぎないものです。
私はBTOショップでこの構成を実際に導入しましたが、購入前は「本当にここまで差が出るのか」と半信半疑でした。
ところが使い始めてすぐ、安定性の大事さを思い知らされました。
ゲーム中だけでなく、配信や動画編集などの作業時も止まらずスムーズに動作してくれるため、これまでのようにメモリやストレージの読み込み詰まりに苛立つことがなくなったのです。
だからこそ私は、このCPUの真価が最も輝くのは4K環境だと自信を持って言えます。
WQHDやフルHDでも余裕を見せますが、他のCPUとの差を「体感レベルで実感できる」瞬間はやはり4Kでの利用なんです。
一度この環境に慣れてしまった今、以前の構成に戻る気にはなれません。
戻れないですね。
では、どうするべきかと問われれば答えは単純です。
4K環境を前提にPCを組む。
そのうえでRyzen 9800X3Dを採用すれば、GPUの性能が存分に引き出され、余計な心配をせずに理想のゲーミング体験に没頭できます。
もう迷う必要はないでしょう。
AI補間やレイトレーシングをオンにしたときの実感
Ryzen 9800X3Dを実際に使ってみて、私は率直に「これは信頼できるCPUだ」と感じました。
今までいくつもハイエンドCPUを試してきましたが、その中でも群を抜いて安定している印象があります。
どんなに負荷のかかる場面でも落ち着いて動作し、ゲームの流れを邪魔しない。
これこそが私にとって一番大切なポイントでした。
まず、ゲームをしていてすぐに気づいたのは映像の滑らかさです。
これまでの環境では華やかなエフェクトが重なる瞬間、どうしても映像に引っかかるような動きが混ざることがありました。
まるで余裕をもって処理しているかのように、落ち着いた映像を届けてくれるのです。
私はその瞬間、初めてPCゲームに安心感を覚えたと言っても過言ではありません。
特にレイトレーシングを最大限に有効化した夜景のシーンでは違いが顕著でした。
雨に濡れたアスファルトに街の灯りが映り込み、ガラスや金属が自然な反射を見せる。
以前なら処理落ちでせっかくの映像が台無しになることが多々ありましたが、今回は粘るようにフレームが安定を保ち、映像の世界に没頭できました。
心の底から「あぁ、これでやっと本物の臨場感を体験できる」と感じたのです。
AI補間の効果も驚きでした。
DLSSやFSRを使うと映像は軽くなるけれど、不自然さを覚えることが少なくありませんでした。
それがこのCPUではフレームの切り替わりが滑らかで、まったく不自然に感じないのです。
フレームが60から120に切り替わるとき、まるで視界を広げる風を浴びたような爽快さがありました。
作られた映像ではなく、生きた動きを目で追っているような感覚に浸れる。
これは非常に大きな安心材料になりました。
遅延についても意外な発見がありました。
私は正直、AI補間は入力ラグのリスクを伴うと思っていたのですが、実際にはそうした違和感がまったくありませんでした。
マウスの挙動もキーボードの入力も、一切の遅れなく映像に同期していたのです。
その自然さに、思わず「これはすごい」と口にしてしまいました。
そして静音性についても触れたいです。
高性能CPUをフルに使えば騒音が増すのは当然だと思っていたのですが、私の環境では空冷クーラーだけで十分に抑えられました。
長時間のプレイでも耳障りなファンの唸りに悩まされなかったのは、本当に快適でした。
省電力設計の効果を実感しつつ、「これで本当に全力で動いているのだろうか」と疑いたくなるほど静かでした。
映像表現の面でも心を動かされました。
爆発の光が部屋全体を一瞬で照らし、壁や床に自然に反射していく様子に思わず感嘆の声が出てしまいました。
その表現がリアルタイムで成立していることに驚き、映像作品の説得力をここまで高めるのかと納得しました。
実際に録画したシーンを見返したとき、映像に込められたメッセージ性が一段も二段も強まっていたのです。
これなら視聴者もきっと心を動かされる、と確信しました。
課題もあります。
AI補間とレイトレーシングを同時に最大限活用すると、GPU負荷と消費電力は確実に跳ね上がります。
ただ、このCPUはそうした重い処理を冷静に受け止め、全体のバランスを維持してくれるのです。
システム全体が不安定に傾かず、むしろCPUが全体の舵取りを担っているように感じました。
これはなかなか得がたい強みです。
私が最終的に強く感じたのは、「このCPUなら長く信頼できる」ということです。
重いゲームでも配信でも落ち着いて対応できる余裕がある。
どんなに性能の高いGPUを用意しても、CPUが息切れしては全体の力は半減してしまいます。
しかしRyzen 9800X3Dに任せておけば、そのGPUの力をフルに引き出し、実際以上のパフォーマンスを体感させてくれるのです。
だから私は、このCPUを自信をもって人に勧めたいと思いました。
AI補間やレイトレーシングを突き詰めたプレイを実現したい方にとって、これが最も近道になるでしょう。
高解像度、高fps、そして長時間遊んでも揺るがない安定感。
それが実際に体験した私の答えです。
心地よさ。
安定感。
こうしたものが揃ったとき、人の記憶に残るのは単なる数字やスペック表ではなく、自分が体験した「その時間」なのだと実感しました。
私は、このCPUのおかげでゲームが単なる娯楽から特別な体験へと変わる瞬間を味わいました。
そうした確かな価値を、同世代のビジネスパーソンにもきっと理解してもらえるはずです。
Ryzen 9800X3D 搭載PCを組む際に考えたいパーツ選び
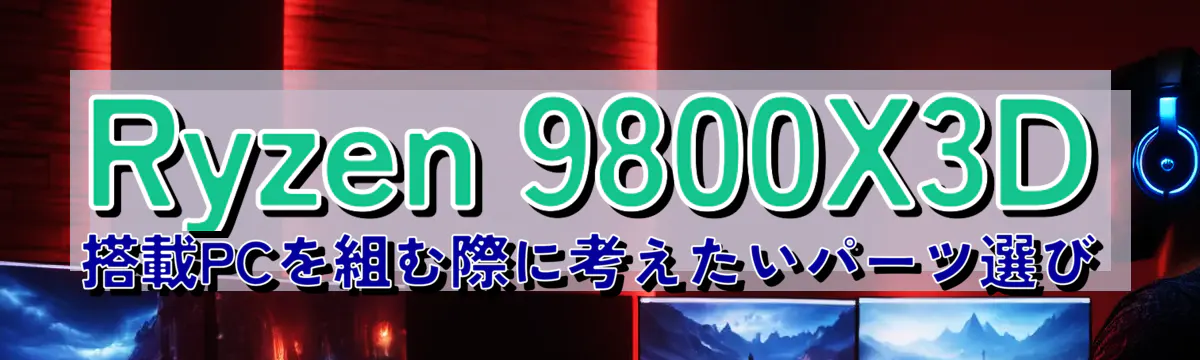
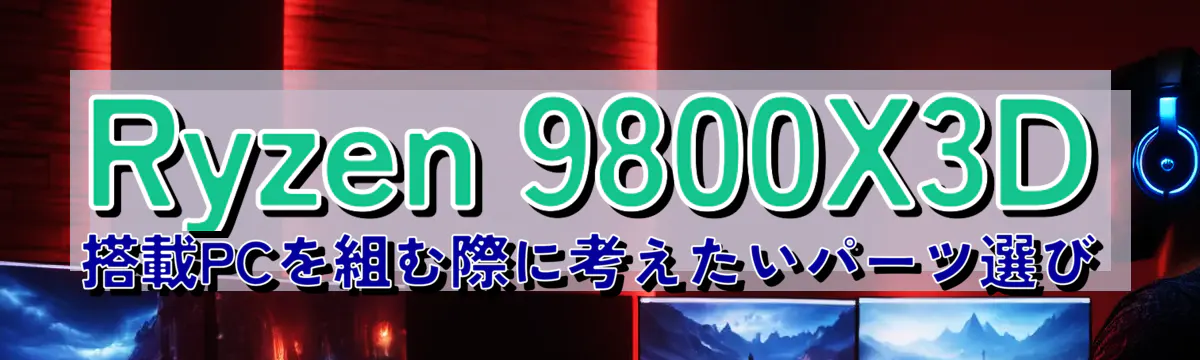
DDR5?5600メモリを32GBと64GBで比べてみた体感差
ざっくり言えば、ゲーム中心なら32GBで十分ですし、配信や動画編集などを絡めた作業が多ければ64GBを選んだ方が結果的に快適でした。
ゲームだけで見ると、32GBで全く不自由を感じませんでした。
フレームレートも極めて安定していて、描画も滑らか。
正直なところ「32GBがあれば他はいらないんじゃないか」と思えるくらいです。
GPUの力を余すことなく引き出す分にも不足はなく、普通にゲームを遊ぶ分には十分すぎる環境でした。
ですが話が変わるのはマルチタスクです。
例えば私は動画編集をしながら裏でエンコードを走らせ、さらにその合間に配信をしたりブラウザで資料を探したりします。
そんなとき、32GBだと妙に挙動が引っかかる瞬間が出てくる。
「あれ? 今処理が止まった?」と声に出すくらいの違和感です。
タスクマネージャーを開いてみたらメモリが30GB超。
余裕がほとんど残っていなかったんです。
64GBに切り替えてからはそうした違和感がほぼなくなり、マルチタスクの状態でも余裕がしっかり保てました。
まさに安定感の違い。
安心感にも直結しました。
気持ちの余裕まで違ってきます。
特に編集作業では差が顕著でした。
4Kの素材を並べ、カラー補正してエフェクトを重ね、さらにテキストを追加し…といった複雑な負荷をかけると、32GBでは裏で開いているソフトが処理落ちし、再読み込みのたびにこちらのリズムが乱されます。
「また待たされるのか」と思う時間が増えて集中力はガタ落ち。
ところが64GBにすると、それが嘘のように滑らかに進む。
余裕がバッファとして働き、作業が気持ちよく回るんです。
この変化は本当に大きかったです。
それでもゲーミングだけのために64GBにする意義は薄い、と私は思っています。
ゲーム体験を左右するのはGPUやストレージ性能の方が大きく、メモリを32から64に増やしてもフレームレートや描画が劇的に変わるわけではありません。
実際に費用対効果を考えれば差額をグラボやNVMe SSDに充てた方が満足度は高いでしょう。
ゲーマーにとって賢い選択はそちらです。
納得感があります。
ただ、私自身の体験で痛感したのは安定性の意味です。
以前32GB環境で複数の編集ソフトを同時起動していたら、どうしてもアプリが落ちてしまい作業が中断、やり直しを強いられました。
効率は最悪で、イライラが重なりミスも増える。
64GBにした瞬間、それがピタッと解消されたのです。
「まるで別物だな」と思わず漏らしたほどでした。
それ以来、私はメモリ容量をただのスペック表の数字としては見なくなりました。
作業効率やストレスに直結する実感値なんです。
ここでCPUとの相性の話を補足します。
Ryzen 9800X3DとDDR5?5600の組み合わせは非常に安定感があり、キャッシュ構造の強みでメモリ帯域の不足に引っ張られることがほぼありません。
つまりCPUの力をしっかりと引き出せる。
32GBでも64GBでも、DDR5?5600を選んでおけば土台がしっかりしているので安心できます。
これは重要なポイントです。
だから最終的な判断はシンプルになります。
ゲームだけなら32GBで充分です。
でも動画編集や配信、ブラウザやアプリを数多く同時に動かしながら仕事をするなら迷わず64GBがいい。
無駄な投資は避け、必要な部分にしっかり資金を振り向けること。
これが最適です。
私の場合、その選択をしたことで仕事もプライベートも効率が高まり、ストレスが減りました。
お金をかける価値があるのかどうか悩んだ末に気づいたのは、この選択は性能のためだけではなく、精神的な余裕を買う意味があるということです。
快適さ。
効率性。
9800X3D搭載PC搭載ゲーミングPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R66V


| 【ZEFT R66V スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Okinos Mirage 4 ARGB Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61G


| 【ZEFT R61G スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R67I


| 【ZEFT R67I スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH160 PLUS Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R62E


| 【ZEFT R62E スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9070XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H6 Flow White |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60FC


| 【ZEFT R60FC スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5080 (VRAM:16GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal Design Pop XL Air RGB TG |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 1000W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (アスロック製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
ストレージはGen4 SSDとGen5 SSDのどちらが良いか
しかし実際に日常の作業に落とし込んで考えてみると、Gen5の性能をフルに生かせる場面というのは、驚くほど限られているのです。
正直に言えば、新しいものが好きな私ですら「これは実用というより、先行投資に近いな」と思わされました。
例えば、14,000MB/s近い転送速度を誇る環境を試したとき、数字の迫力に圧倒されはしたものの、普段の作業で体感的に「劇的だ」と感じる瞬間は案外少なかったのです。
私は動画編集を日常的に行っていますが、大容量のファイルを扱うときに本当に違いを感じるのは、結局Gen4の7,000MB/sクラスでも十分だという場面ばかりでした。
むしろGen5では発熱量が増え、その冷却対策を気にしなければならないことが増えてしまいました。
この印象がどうしても拭えません。
ケース内部の通気や追加ファンの必要性に悩むぐらいなら、安定して使えるGen4の方が精神的にも余裕を持てます。
私は今もCrucial製の2TB Gen4 SSDをメインドライブに据えて使っています。
4K動画を1日に数本扱っても処理が途切れたり動作がもたついたりという場面はほとんどなく、冷却を意識して神経質になる必要もありません。
追加のヒートシンクに頼らなくても作業環境がきちんと安定してくれる。
この安心感は予想以上に大きな価値があると私は感じています。
普段の仕事や趣味の中で余計な心配事を抱えなくて済むことが、パフォーマンスの数字以上にありがたいことなのです。
一方でGen5 SSDを選ぶ意義がまったくないわけではありません。
大容量データを複数同時進行で処理しながら配信もこなすような環境ですと、間違いなくGen5の帯域は助けになるでしょう。
それよりもむしろ、巨大なヒートシンクがケース内のエアフローを妨げたり、冷却ファンがうるさく回り続けて集中を削がれたりする面倒の方が気になります。
熱い、そしてうるさい。
どうしてもこの二つがつきまとってしまうのです。
市場でGen5 SSDが普及し始めていることは知っています。
ショップのBTOモデルでも組み込まれるケースが増えていますが、見積もりを見たときに「ここまで価格差があるのか」と驚きを隠せませんでした。
正直なところ、この差額があるならGPUやメモリに資金を回した方が確実に体感を得られます。
ストレージ部分に過剰投資するより、全体のバランスを考えて安心できる構成にしたほうが賢い。
私にはそう思えてなりませんでした。
実際に試験的に使用しているRTX 5070Ti構成のPCには2TBのGen4を搭載しましたが、ゲームのロードも軽快で、アプリの起動も快適そのものです。
ストレスを意識しないで済む安心感こそが、毎日の作業や遊びへのモチベーションを安定的に支えてくれるのだと実感しています。
「あ、これで十分だ」と思えた瞬間、この選択に間違いはなかったと確信しました。
もちろん、未来を見据えるならGen5 SSDにも期待できる点はあります。
例えばAI系のワークロードのように、数百GB単位の学習データを瞬時に処理するような作業では、その広い帯域は大きな意味を持ちます。
私も実際に生成AIを走らせていて、「あ、ここがボトルネックになっているな」と感じる瞬間が確かにありました。
いずれはGen5が標準になる未来は来るでしょうし、そのときには冷却や静音設計も新しい世代の工夫によって自然に解決されていくと思います。
進化のプロセス。
ただし、その未来が訪れるとしても、今この時点でユーザーが取るべき賢明な選択はやはりGen4です。
2TBクラスをシステムと作業両方に据えて、追加が必要なら外付けSSDやHDDで補う。
これが一番負担なく、コストもパフォーマンスも程よい構成です。
そして何より、使う側が安心して日々のタスクに集中できる。
安心できる道具であることが、一番の価値なのです。
仮にRyzen 9800X3DのようなハイエンドCPUを導入したとしても、SSDに関してはGen4を組み合わせる方がバランスが良いと私は強く思います。
無理にGen5を選んで冷却や騒音と戦うより、落ち着きのある環境で確実に作業を進められる方がよほど豊かな体験につながるからです。
PCは道具であり、長く付き合うパートナーです。
快適で静かに、しかし確実に力を発揮してくれる存在であってほしい。
私はそこにこそ、本当の意味での快適さがあると信じています。
未来志向がGen5、バランスがGen4。
人によって答えは分かれるでしょう。
けれど私の意志はもう固まりました。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
静音性重視なら空冷と水冷、どっちにするべきか
性能や静音性のバランスを考えると、多くのケースでは水冷よりも空冷の方が扱いやすく、安心して長時間向き合える環境を作れるからです。
もちろん水冷の長所を否定するつもりはありませんが、仕事と趣味の両面でPCを酷使してきた実感として、静けさを求めるなら空冷を優先するべきだと考えています。
最近の空冷クーラーは本当に進化しました。
昔は「大型の水冷こそが正解」という雰囲気がありましたが、今は違います。
ヒートパイプの効率、フィンの形状、ファンの精度などが年々改良され、静かにしっかりと熱を逃がしてくれる。
水冷より安価でトラブルも少なく、静けさを求める人にとっては大きな魅力です。
静音性。
これは夜中に仕事をする私にとって最大の恩恵であり、深夜の部屋で集中し続けるための条件そのものです。
もちろん、水冷の強みを認めないつもりはありません。
ケース内部の熱を外に直接排出できる効率性は確かで、CPUとGPUを同時に負荷をかけるような場面では、水冷のポテンシャルを感じることが多々あります。
特に配信をしながら重い処理を動かすときなどは、空冷ではやや温度が心配になる。
ただ、そこで気になるのがポンプ音。
小さな振動音が夜の静けさを邪魔する瞬間があり、私はどうしてもその違和感から逃れられませんでした。
音は数字で測れない厄介な要素であり、だからこそ人によって評価が大きく変わるのだと思います。
数年前、私はCorsairの280mmの簡易水冷を長期間使っていたことがあります。
真夏でもCPU温度は安定し、レンダリング中も一切不安にならない。
その性能に大満足していたはずなのに、深夜の作業で気になるのは「かすかなポンプ音」。
結果、次のアップグレードで大型の空冷クーラーに戻したのです。
大げさに聞こえるかもしれませんが、そのとき私は自分が「性能数値よりも生活の静けさを重視する人間」だと、ようやく本気で理解しました。
そういう環境になると水冷は非常に効果的ですし、静音ファンを組み合わせれば日常使用レベルで十分静かに仕上げることも可能です。
むしろデザインを優先しながら性能を維持する、その柔軟さこそが水冷の強みではないでしょうか。
ここで無視できないのが、CPU以外の発熱です。
たとえば9800X3Dの世代では、TDPの観点からも空冷で十分やっていけるシーンが多いですが、その一方でNVMe Gen5 SSDのように発熱の激しい部品が当たり前になりました。
これらはヒートシンクを必須とし、状況によっては補助ファンが必要になります。
パソコン全体を一つの「熱を抱えるシステム」として見ないと、せっかく静かに仕上げてもどこかで小さなノイズが増えてしまう。
そのバランスを取るのが本当に難しいのです。
私なりの一番のおすすめは、エアフローに配慮したケース選びと高性能な空冷クーラーの組み合わせです。
ファンのサイズや配置を丁寧に調整してやれば、負荷をかけても驚くほど静かに運用できます。
静かな空間で仕事に没頭できる安堵感、マイクに雑音が乗らない信頼感、そうした価値はスペック表には決して書かれていませんが、日々の作業環境を支えてくれる重要なポイントです。
夜に集中して仕事していると、この静音性のありがたみが心から実感できますね。
率直に言えば、水冷は「見た目の格好良さ」と「排熱効率」の両方を求める人には最高です。
しかし私自身は空冷を選び続けています。
理由は単純で、自分の生活リズムと感覚に合うから。
パソコンは趣味の道具というより生活の一部です。
息が合う、長く一緒にいられる。
そう考えれば、性能と同じくらい「音との付き合い方」が重要になる。
だから私は空冷を優先したのです。
まとめるなら、9800X3Dを静かに使いたいなら空冷が第一。
静音性を真剣に追い求める人にとって、空冷は一歩先を行く存在。
水冷は「デザインや構造との折り合い」で役立つ存在。
そのすみ分けこそが私の答えです。
空冷を優先。
夜の作業部屋に響くのは、ファンが空気を送るやわらかな音だけ。
そんな環境こそ求めていたものです。
静けさ。
落ち着き。
これ以上の贅沢はありません。
パソコンは相棒です。
性能と同じくらい、寄り添える静けさが必要です。
Ryzen 9800X3D 搭載PCについてよく寄せられる質問


動画編集を始めたばかりでも扱いやすいのか?
動画編集に本気で取り組もうとするなら、Ryzen 9800X3Dを搭載したPCは安心して選べる選択肢だと私は感じています。
大げさに聞こえるかもしれませんが、処理の速さがそのまま作業効率や気持ちの余裕に直結するのです。
私はこれまで幾度となく「読み込み待ち」や「再生の引っかかり」に耐えてきましたが、正直なところ精神的な消耗が大きかった。
9800X3Dを導入してからはそうした無駄な時間が大幅に減り、結果として編集に前向きに取り組めるようになったのです。
効率だけではなく、心のゆとりに直結する安心感。
これが一番大きいと実感しています。
仕事帰りに少し動画をいじるのが習慣になりつつあるのですが、以前の環境だとソフトの立ち上げさえ気が重かったんです。
待つあの数十秒が本当に嫌でした。
しかし今では数秒で立ち上がり、気軽に取りかかれる。
気持ちの切り替えがスムーズにできるので、その日の疲れが少し薄れるような感覚さえあります。
軽やかに進む作業の流れ。
それが気持ちを楽にするのです。
もちろんフルHD編集は余裕ですが、4K素材になるとそれなりの負荷がかかります。
それでもCPUのスレッド性能や大きなキャッシュのおかげで、細かいカットや字幕入れはサクサク動く。
正直、昔なら重さにうんざりしていた場面で「これなら大丈夫だ」と落ち着いて構えられるのです。
作業中に感じるストレスが小さいことが、どれだけ継続意欲につながるか。
これは体験してみないと伝わらない部分だと思います。
ただしCPUだけで快適な環境が出来上がるわけではないと、私は改めて学びました。
GPUとして組み合わせたのはRTX 5070Ti。
映像のエンコード速度やノイズ除去の精度が目に見えて変わり、CPUの性能をグッと引き上げてくれる印象があります。
環境全体が後押ししてくれる安心感は、机に向かう自分の気分をも変えてくれるんです。
これこそ「全体最適」の力。
CPU単体の凄さではなく、総合的な噛み合わせの良さに支えられる。
メモリの選択については悩みました。
最初は16GBで十分だろうと軽く考えていたのですが、ブラウザや補助アプリを同時に立ち上げると途端に重くなる。
思っていた以上にストレスが溜まりました。
結局32GBに増設してやっと落ち着いたわけですが、「最初から投資しておけば」という後悔が残ったのも事実です。
32GBを導入した瞬間に世界が変わったような安心感を得られたとき、背中からスッと荷物が降りた気がしました。
ストレージにはGen4対応のNVMe SSDを2TB入れましたが、この効果も大きいです。
素材用と作業用を分けるとプロジェクトの読み込み時間が一瞬早くなり、そこで思わず「おおっ」と声に出してしまいました。
レンダリングの待ち時間が明確に短くなった瞬間は心底嬉しくなります。
小さな積み重ねが気分を軽くしてくれるわけです。
熱対策についても気にしていましたが、9800X3Dは意外にも空冷で十分でした。
サイズ製のクーラーを取り付けたところ驚くほど静かで安定していて、動画編集では十分な冷却性能を発揮しています。
編集はゲームのように常時全開で動くわけではないので、安定感があれば必要以上の不安は感じません。
「静かで涼しい」。
この二つを同時に満たした環境は、作業そのものを心地よい時間へと変えてくれました。
ケースはピラーレスのガラスパネルを選びました。
性能に直結する部分ではないのですが、見た目の良さは思わぬやる気を与えてくれるものです。
意外と大事なんですよ、こういう動機付け。
結果として、日々コツコツ編集スキルを磨ける自分につながったのです。
とはいえ注意も必要です。
CPUが高性能でも、ソフトによってはGPU側に作業を大きく依存する場面があります。
派手なエフェクトや複雑なレンダリングはGPUに任せた方が圧倒的に速い。
ここを理解しないままCPUだけに過度な期待を寄せると、肩透かしを食らいます。
9800X3Dはあくまで「土台」。
支える存在であって、派手に見せる花火を打ち上げるのはGPUなんです。
そういう住み分けを理解すると安心して使えます。
その流れで編集にも使い始めたのですが、9800X3Dは期待以上に頼もしい相棒でした。
軽めのカット編集や配信用の動画はストレスなくこなせますし、何より「余計な苦労を強いられない」ことが本当に大きいんです。
編集には集中力が求められるからこそ、無駄な負担を排除してくれる環境に助けられました。
将来的にはさらにGPUやメモリの発展が進み、CPUキャッシュを効率よく使うソフトウェアが増えていくはずです。
そのとき9800X3Dはゲーマーだけではなくクリエイターにとっても魅力ある選択肢になると私は考えています。
ゲームも編集もどちらも支えてくれる存在。
最終的には人それぞれのスタイル次第だと思います。
ただ私にとって、このPC環境は動画編集を始めるうえで大きな安心を与えてくれました。
そしてその安心感は、学ぶ意欲とチャレンジする勇気へとつながっていきます。
ゲームと配信の同時利用は本当に安定するのか?
正直、ここまで安定感が増すとは思っていなかったのです。
配信をしながらでも映像が途切れずに進んでいく、その安心感に初めて触れたとき、心の中で長く抱えてきた不安が溶けていくようでした。
これまでなら配信ソフトがCPUに過大な負担をかけ、すぐにフレーム落ちが発生していました。
ところがRyzen 9800X3Dを使った途端、OBSで確認してもドロップフレームがゼロか、あっても数フレーム程度に収まるという結果に驚きました。
「こんなに違うものなのか」と思わず声が出ました。
数字も裏付けになりましたが、実際の操作感の中で映像が途切れないことの大きさは、何よりも配信者にとって心強いものです。
もちろん、このCPUが万能というわけではありません。
設定を限界まで引き上げればGPU側が先に音を上げる場面もあります。
しかし少なくともCPUがボトルネックになることがほぼ消えたのは確かです。
仕事に置き換えて考えると、まるで力強い同僚が黙って裏で支えてくれているような安心感すらありました。
頼もしさとは、こういう感覚です。
実験はさらに続きます。
配信を流し続けながら、同時に動画編集ソフトで書き出しを行いました。
これまでのCPUだと、すぐ配信映像が止まり「配信落ちた?」というコメントが飛んできたものです。
しかし、このCPUでは同時進行していても配信が途切れない。
いつもは気をもみながら行っていた複数タスクが、こんなに軽やかに回るなんて。
これは長年パソコンをいじってきて初めての体験でした。
そして気になる発熱についても試しました。
TDP120Wクラスという数字だけを見ると身構えますが、実際には空冷で70度前半に収まるシーンが多い。
私は水冷よりも空冷派で、できればシンプルな環境にしておきたい、という考えをずっと持ってきました。
真夏の暑い日でも数時間配信ができたとき、「これは安心して続けられる」と心から思いました。
長時間作業の途中で熱暴走が頭をよぎらないだけでも、心理的な余裕が全く違います。
一点だけ気になった場面もありました。
配信を4K解像度にした時です。
特に60fpsで高品質エンコード処理を同時に行うと、時折わずかに映像が引っかかる瞬間がありました。
つまり、余裕を持たせる使い方が一番の安定のコツ。
これは配信に限らず、ビジネスの現場でも通じる学びだと感じます。
最近はAIによる背景やアバターを取り込んだ配信も珍しくなくなってきています。
私もAI生成の背景をOBS上で加えて動かしてみました。
しかし今回は映像が止まらず滑らかに動き、普通に進行できたのです。
このCPUにはまだまだ余裕があると確信できた瞬間でした。
この余力が、これからの新しい配信スタイルには大きな武器になります。
数時間にわたりテストしましたが、何より印象に残っているのは、配信中に「ラグった」とか「映像飛んだ」といった視聴者からのコメントが一度も無かったことです。
これは私の配信歴の中でも非常に珍しい出来事でした。
安定して続けられること。
それこそが配信の命だと強く思います。
私は以前からAMDに親しみを持ってきました。
このCPUを軸にすることで、ゲームも配信も制作作業も、無理なく同居させられる。
そのバランスの良さは40代を生きる私にとって、仕事と趣味の両面で信じられる要素でした。
無理に尖らせない、けれど確かな力を発揮する。
結局、私が長い時間をかけて探してきたのは、そんな存在なのかもしれません。
全体をまとめるなら、Ryzen 9800X3Dを中心に自分の作業環境を組み上げることが、安定配信を求める人にとって有力な選択肢になります。
これは宣伝文句ではなく、実際に汗をかいて試した結果であり、ようやくたどり着いた実感なのです。
実務にも遊びにもきちんと寄り添い、背伸びをせずとも快適にしてくれる。
それは私が今求めている理想的なパートナー像と重なります。
安心感がありました。
頼れる力を感じました。
配信という趣味を超えて、長く付き合える確かな道具に出会えた気がしています。
9800X3D搭載PC搭載ゲーミングPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R61GF


| 【ZEFT R61GF スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60HV


| 【ZEFT R60HV スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61FC


| 【ZEFT R61FC スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9060XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | INWIN A1 PRIME ピンク |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850I Lightning WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60SM


| 【ZEFT R60SM スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60CRB


| 【ZEFT R60CRB スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | be quiet! SILENT BASE 802 Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
Ryzen 9800X3DとCore Ultraシリーズを比べたときの注目点
明確に言えることは、ゲームを本当に満喫したいならRyzen 9800X3Dが頼りになるし、仕事や配信といった複合的な作業を優先するならCore Ultraシリーズが安心だということです。
どちらも触ってみて分かったのは、同じCPUでもこんなに性格が違うのか、と驚かされるほどの個性があるということでした。
Ryzenを試したときにまず驚いたのは、フレームの安定性です。
特に敵が一気に出てくる派手なシーンでも画面が乱れず、プレイが途切れない。
私は長くPCゲームをしてきましたが、このレベルの安定感はなかなか出会えません。
初めて体感したときには思わず「これは反則級だな」と呟いていましたね。
FPSや高解像度のタイトルならなおさら効果が顕著で、スペックの数字以上に安心して遊べる感覚を提供してくれます。
一方で、Core Ultraシリーズには全く別の良さがありました。
例えば、配信を流しながら映像編集を同時進行するようなシチュエーション。
ファンの音も控えめで、長時間の作業でも集中を途切れさせない。
こうした「静かさ」と「効率性」の両立は、やや大げさに聞こえるかもしれませんが、ビジネスの場面でも間違いなく頼れる相棒になると思います。
正直言うと、私は動画編集もRyzenでは荷が重いだろうと最初は思っていました。
ところが、タイムラインを快適にスクラブできて、操作感が軽快だったんです。
キャッシュ設計のおかげで、かなり快適に動いてくれるのです。
逆にCore Ultraのほうは、複雑なエフェクトを重ねても滑らかさを失わず、AI機能が実際の作業効率をぐっと後押ししてくれる。
こうなるとどちらが優れているという発想ではなく、それぞれの「尖らせ方の違い」に気付かされます。
もしGPUと組み合わせるならどうでしょう。
最新のRTX5070TiやRadeon RX 9070XTと組み合わせたとき、Ryzen 9800X3Dはゲームのフレーム性能を極限まで引き上げてくれる。
ゲーマーにはこの伸びやかさが本当に魅力です。
他方、Core Ultra 7や9と合わせるなら、AI処理の補助が効いて作業負荷が自然に振り分けられるので、日中は仕事の資料編集をこなして、夜に配信や映像作業にも手を伸ばす、といった多用途のライフスタイルと好相性です。
「一日走らせても疲れが出ない」と感じたのは事実です。
長くPCに触れてきた私でも、Ryzenの瞬発力には心底惹かれました。
まさにゲーマーに全力で応えようとする潔さがあります。
ただ、仕事で複数の資料を同時に編集したり、裏で配信録画を走らせたりする場面では、Core Ultraの効率性が頼もしい。
場面によってどちらを選ぶか頭を悩ませる瞬間が多々ありました。
ですが、最終的には「自分が何を大事にするのか」そこに尽きます。
ゲームで一切妥協したくないのか。
それとも幅広い作業を同時進行でこなしたいのか。
完璧なCPUなんて存在しませんが、どちらにも惚れる瞬間がありました。
私はゲームに没頭したいのでRyzenを選びましたが、それは私にとっての正解であって、誰にでも通じる答えではありません。
それでも両者をじっくり触れてみて強く感じたのは、Ryzenの切れ味とCore Ultraの粘り腰はまるで異なるベクトルで磨き込まれていて、どちらも利用者に寄り添う力をもっているという点です。
結局はどちらを選んでも後悔はしないだろうという安心感が残りました。
私は最後に、ゲーム好きだからこそRyzen 9800X3Dを選びました。
それぞれのCPUは使う人の選択に正直に応えてくれる。
これだけは胸を張って言えます。
長期間使うなら空冷と水冷、どちらが安心か?
たしかに水冷の冷却性能や静音性は非常に魅力的で、導入当初はそのスマートさや能力の高さに感心したこともあります。
しかし、どうしても「もし故障したらどうなるのだろう?」という不安が頭をよぎってしまう。
これが長期利用の現場ではやはり大きな問題になるのです。
特にポンプが止まるリスクや、ホースの劣化、冷却液の蒸発といったトラブルは、いざ起こってしまうと対応が面倒ですし、仕事の最中でそういう事態に直面すると精神的なダメージはかなりのものです。
水冷を使っていた時期、レンダリング作業中に「これ、本当に最後まで持つんだろうか」と無意識に心配してしまったことがありました。
静音性やピーク時の冷却能力は確かに素晴らしい。
でも本当の安心には届かない。
逆に空冷は、構造が単純で壊れる要素が少なく、その分長く安定して働いてくれます。
ファンという物理的に動く部分こそ消耗しますが、取り替えも簡単で部品も手に入りやすい。
自分の手で何とかできる範囲に収まるのはやはり大きな魅力です。
派手ではない。
でも安心できる。
これが空冷の持つ強みですし、長時間PCを動かし続ける環境ではその堅実さが何よりも価値になるのだと改めて感じます。
Noctuaの大型クーラーを導入したときは、正直感動しました。
Ryzen 9800X3Dを数時間フル負荷で動かしても温度に不安を感じることはなく、静音性も予想以上。
機械が淡々と仕事をし続けてくれる姿を見て、思わず「これ以上に欲しいものがあるのだろうか」と心の中でつぶやいてしまったほどです。
何時間も動画のレンダリングが走っていても、不快な音に邪魔されることがなく、その時間を心地よく過ごせること自体が大きな価値。
安心して任せられる道具であることに、深い信頼を覚えました。
もちろん、水冷の魅力を否定するつもりはありません。
見た目の美しさやスマートさは唯一無二で、特にガラス張りのケースでは映えますし、空気の流れが制限される構造では水冷のほうが適している場合もあるでしょう。
私自身もある時期、そのかっこよさやパフォーマンスに惹かれたことがありました。
しかし、結局のところ私は「仕事のパートナーには安定していてほしい」との思いに戻ってきた。
気持ちの揺れこそありますが、現実的に見れば自分に合うのは空冷です。
昔と比べると静音性が格段に高く、エアフローとの相性さえ工夫すれば、高負荷作業でも十分な性能を発揮してくれる。
数時間に及ぶ配信や動画編集をするときでも耳障りな音がほとんどなく、気持ちを切らさずに作業に集中できました。
社会人として日々忙しく過ごす以上、この小さなストレス軽減が本当にありがたいのです。
それに、空冷なら自分のスケジュールに合わせてファン交換など簡単なメンテナンスを進められます。
水冷のように突然のトラブルが発生して仕事を止める可能性を抱えるよりは、先回りして予防できる方がずっと安心。
無駄な出費や時間を削れることにもつながります。
限られた時間の中で効率よく成果を出したい立場だからこそ、この要素は大きいです。
性能を限界まで追い求めたい人や、カスタマイズそのものを楽しむ人にとっては水冷は面白い選択肢だと言えるでしょう。
しかし、私のように仕事で毎日酷使するPCを長く安心して動かしたい人には、やはり空冷こそが最も現実的で賢明な手段だと確信しています。
安心できる相棒。
頼れる冷却。
私が最終的に選び取るのは、結局この二つを満たしてくれる空冷なのです。
数字よりも体感としての安心感。
見栄えよりも長期的な信頼性。
Ryzen 9800X3DクラスのCPUだからこそ、その性能を活かすために必要なのは確実に稼働し続ける安定した冷却環境であり、私にとってそれを叶えてくれるのは空冷以外にないのです。
購入や構成時によくあるつまずきとその回避方法
Ryzen 9800X3Dを軸にゲーミングPCを組んだとき、私が痛感したのは「性能の良さは組み合わせ次第で簡単に台無しになる」という現実でした。
最初は浮かれていました。
最新のCPUを手に入れたんだから、他のパーツはそこそこのもので十分だろう、と軽く考えていたのです。
しかしその甘い見通しは、すぐに現実に打ち砕かれました。
まず最初につまづいたのはメモリでした。
正直、クロックの高さや容量の違いなんて大差ないだろうと思い込んでいました。
当時の私は「どうせゲームと配信ができれば十分じゃないか」と軽く決めてしまい、結果として中途半端な性能のメモリを選んだんです。
そのときの後悔は今でも鮮明に覚えています。
負荷をかけるとゲームがカクつき、せっかくの9800X3Dの魅力がまるで発揮されない。
自分の浅はかさに呆れながら、「やってしまったな」と小さくつぶやきました。
発熱が控えめと評判の9800X3Dだから大丈夫だろうと楽観して、それほど高くない空冷モデルを選んだのです。
値段も手頃で「おそらく大丈夫」と思ったあのときの判断は、今思えば完全に油断でした。
実際にゲーム配信や動画編集を長時間続けると、CPU温度は静かに上昇し、ファンの音は耳障りなくらい目立ちました。
せっかく集中したいのに、ゴーッと唸る音に気が散ってしまいイライラが募る。
最終的には冷静に諦めて水冷に乗り換えましたが、最初からきちんと投資すべきだったと心底感じました。
やっぱり妥協は駄目ですね。
ケース選びでも同じような落とし穴が待っていました。
私は見た目に惹かれ、木目調の美しいケースを導入しました。
高級感があって、リビングに置いても違和感がない。
最初は誇らしい気持ちでいっぱいでした。
ところが、中を組み込む段階になると後悔が押し寄せました。
内部は窮屈で、GPUを差すだけで汗をかきながら格闘する羽目になったのです。
あのとき、「これは完全に自己満足の失敗だな」と苦笑いしました。
パソコンは家具じゃない。
性能とメンテナンス性があってこそ価値がある。
痛いほど理解しました。
意外と軽視しがちなのがグラフィックボードとのバランスです。
9800X3Dがどれだけ優秀でも、ボードが追いつかなければ無駄になります。
私は4K配信をやりたいという欲張った計画を立て、ストレージ部分で少し妥協しました。
Gen.4のSSDなら大丈夫だろうと2TB品を選びましたが、ロード時間のテンポが悪くてストレスを感じることが多かったです。
それでも安定性は申し分なく、最終的には納得しました。
ただ本音を言えば、もう少し予算を組んでGen.5を導入しておけばベストだったと思うんです。
そんな感じでした。
電源も見落としやすい罠のひとつです。
750Wあれば十分だと考えた私でしたが、最新GPUの消費電力は想像以上でした。
このとき初めて知ったんです。
電源の安定性こそがPC全体の土台なんだと。
結局850Wに買い替えて落ち着いたのですが、あの葛藤に費やした時間は今でも惜しく感じます。
節約するべき場所を間違えました。
ほんとに。
マザーボードもそうです。
安いモデルを選んだときには「これで十分」なんて言い聞かせていたのですが、使ううちに不安定さが目立ちました。
結局上位モデルに切り替えた瞬間、全ての挙動がスムーズになって、胸の中で「これが本来の実力なんだ」と納得しました。
無駄に買い直して出費がかさみましたが、学んだ価値は大きかったです。
こうして思い返すと、私の失敗の原因は一つではありませんでした。
相性を軽んじたこと。
そして「この程度ならいいだろう」と過小評価したこと。
この二つが常に影のようにつきまとっていました。
どんなに高性能のCPUを選んでも、冷却や電源、ストレージやケース、細部をつなぐパーツの調和を甘く見れば全てが足を引っ張ります。
だから今なら胸を張って言えます。
Ryzen 9800X3Dを本当に活かしたいなら、DDR5-5600で32GB以上のメモリ、信頼できる2TBクラスのGen.4以上のSSD、静音性を考慮した冷却、余裕のあるケース、そしてしっかりした電源。
この各要素への投資を惜しまないことです。
そして、それらを自分の利用シーンに合わせて判断することです。
私は平日の夜に小さな配信を楽しみ、休日には動画編集でじっくり時間を過ごすことが多いです。
そんな生活に合った構成だからこそ、PCはただの道具ではなく、信頼できるパートナーになりました。
本当に思うんです。
安心感こそ宝物。
そして最後に残るのは、愛着です。
人気PCゲームタイトル一覧
| ゲームタイトル | 発売日 | 推奨スペック | 公式 URL |
Steam URL |
|---|---|---|---|---|
| Street Fighter 6 / ストリートファイター6 | 2023/06/02 | プロセッサー: Core i7 8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: RTX2070 / Radeon RX 5700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter Wilds
/ モンスターハンターワイルズ |
2025/02/28 | プロセッサー:Core i5-11600K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce RTX 2070/ RTX 4060 / Radeon RX 6700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Apex Legends
/ エーペックスレジェンズ |
2020/11/05 | プロセッサー: Ryzen 5 / Core i5
グラフィック: Radeon R9 290/ GeForce GTX 970 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| ロマンシング サガ2
リベンジオブザセブン |
2024/10/25 | プロセッサー: Core i5-6400 / Ryzen 5 1400
グラフィック:GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| 黒神話:悟空 | 2024/08/20 | プロセッサー: Core i7-9700 / Ryzen 5 5500
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700 XT / Arc A750 |
公式 | steam |
| メタファー:リファンタジオ | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i5-7600 / Ryzen 5 2600
グラフィック:GeForce GTX 970 / Radeon RX 480 / Arc A380 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Call of Duty: Black Ops 6 | 2024/10/25 | プロセッサー:Core i7-6700K / Ryzen 5 1600X
グラフィック: GeForce RTX 3060 / GTX 1080Ti / Radeon RX 6600XT メモリー: 12 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンボール Sparking! ZERO | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i7-9700K / Ryzen 5 3600
グラフィック:GeForce RTX 2060 / Radeon RX Vega 64 メモリ: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE | 2024/06/21 | プロセッサー: Core i7-8700K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce GTX 1070 / RADEON RX VEGA 56 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ファイナルファンタジーXIV
黄金のレガシー |
2024/07/02 | プロセッサー: Core i7-9700
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Cities: Skylines II | 2023/10/25 | プロセッサー:Core i5-12600K / Ryzen 7 5800X
グラフィック: GeForce RTX 3080 | RadeonRX 6800 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンズドグマ 2 | 2024/03/21 | プロセッサー: Core i7-10700 / Ryzen 5 3600X
グラフィック GeForce RTX 2080 / Radeon RX 6700 メモリー: 16 GB |
公式 | steam |
| サイバーパンク2077:仮初めの自由 | 2023/09/26 | プロセッサー: Core i7-12700 / Ryzen 7 7800X3D
グラフィック: GeForce RTX 2060 SUPER / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ホグワーツ・レガシー | 2023/02/11 | プロセッサー: Core i7-8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: GeForce 1080 Ti / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| TEKKEN 8 / 鉄拳8 | 2024/01/26 | プロセッサー: Core i7-7700K / Ryzen 5 2600
グラフィック: GeForce RTX 2070/ Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Palworld / パルワールド | 2024/01/19 | プロセッサー: Core i9-9900K
グラフィック: GeForce RTX 2070 メモリー: 32 GB RAM |
公式 | steam |
| オーバーウォッチ 2 | 2023/08/11 | プロセッサー:Core i7 / Ryzen 5
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 6400 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter RISE: Sunbreak
/ モンスターハンターライズ:サンブレイク |
2022/01/13 | プロセッサー:Core i5-4460 / AMD FX-8300
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| BIOHAZARD RE:4 | 2023/03/24 | プロセッサー: Ryzen 5 3600 / Core i7 8700
グラフィック: Radeon RX 5700 / GeForce GTX 1070 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| デッドバイデイライト | 2016/06/15 | プロセッサー: Core i3 / AMD FX-8300
グラフィック: 4GB VRAM以上 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Forza Horizon 5 | 2021/11/09 | プロセッサー: Core i5-8400 / Ryzen 5 1500X
グラフィック: GTX 1070 / Radeon RX 590 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |